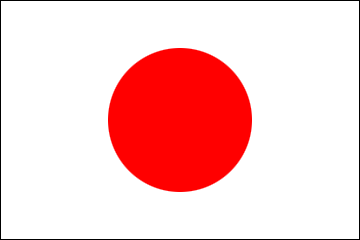メールマガジン2024年9月号
令和6年9月6日
【在セネガル日本大使館メールマガジン 2024/9/6 第28号】
◆ 目次 ◆
1 「伊澤修駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「寄稿文」
4 「領事便り」
5 「政治・経済」
6 「広報・文化便り」
***********************
1 伊澤修駐セネガル日本大使挨拶
8月は雲が多く時々スコールのような雨が降りますが、梅雨のように何日も雨が続くようなことは無く、街中の冠水も幸い2年前の洪水のように深刻ではありません。暑さも東京の暑さに比べるとそれ程でも無いと感じます。皆様如何お過ごしでしょうか。
昨年10月号の挨拶でも述べた通り、カザマンス地方には多くの残置地雷があり地域の復興の足かせとなっています。日本政府は残置地雷の除去に向けた協力を積極的に進めることとし、7月に本使は地雷除去のための特殊ブルドーザー2台等の資機材を供与する無償資金協力についての交換公文に署名をしました。日本企業がこの特殊ブルドーザーを開発しており、この日本の技術がカザマンス地方の地雷除去のために役立つことになります。また、これに併せて8月に自衛隊のOB等が組織するJMASというNGOがカザマンス地方を視察し、退役した元陸上自衛官による地雷除去作業への協力の可能性を検討することになりました。このように我が国は人的協力、物資協力の両面から地雷除去に全面的に協力することになります。
8月の後半から京都精華大学の学生達がフィールドワークのために当地を訪問しています。セネガルにおけるこの研究ツアーは2年前から始まっていて毎年夏に学生達が来るのですが、本使が学生達をお迎えするのはこれで3回目になります。因みに京都精華大学は日本の大学で始めてアニメ学部を設けた大学で、本使もサコ前精華大学学長等からセネガルにおける日本の漫画やアニメを通じた交流の進め方についてアドバイスを頂いています。日本では知られていませんが、セネガルを含め西アフリカは言語、宗教、社会慣習等、社会的文化的に大きな特徴があり研究対象として面白い地域だと思います。今回の学生達の訪問もそうですが、この西アフリカ地域に関心をもつ研究者、そして日本人が増えることを期待しつつお迎えしています。
9月4日より、古屋元セネガル大使の奥様で「手を洗おう会」の代表である古屋典子様がセネガルを訪問しています。典子様にとって久しぶりのセネガル訪問のようですが、今回は「手を洗おう会」の活動の一環で、孫の翠さんが作成した日仏ウォルフ語で書かれた「ディガンテ」という絵本をセネガルの子供達のために持ってきてくださいました。日本人としては母国語である日本語で学校教育を受けることは当たり前のように感じますが、セネガルでは学校教育において多くのセネガル人の言葉であるウォルフ語と仏語をどのように使って教育を進めていくか議論があります。典子様は母国語による教育が重要だと考えていて翠さんとともにこのような絵本を作られたそうです。
言葉と言えば、先日、慶応大学3年生の巴山未麗さんがセネガルに来ました。彼女はセネガルの子供達がしっかりと教育を受けるためには仏語の理解が必要だと考えていて、子供達向けにウォルフ語から仏語を学ぶためのアプリの作成を進めています。まだ若い学生さんがこのような試みを始めていることに本使は心から感心しています。遊びほうけていた遠い昔の自分の学生時代を反省しつつ、今の日本の若者はなかなかやるもんだと思い応援しています。
最後に、9月初めに来年の大阪万博のプロデューサーの一人で「クラゲバンド」のリーダーの中島さちこさんがバンドの皆さんと読売TVの撮影チームと共にセネガルに来ました。万博の「クラゲ館」で放映される映像を撮影するために訪問したそうです。撮影はゴレ島、ダカール市内、ンブールで行われ、特にゴレ島でクラゲバンドはンジャイローズ・ファミリーと一緒に演奏を行いました。ピアニストの中島さんは、6月のゴレ島平和音楽祭の際に寄贈され、現在ゴレ市の文化会館に保管されているピアノを楽しそうに弾いていました。視察や演奏を通じて中島さんはセネガルの雰囲気に圧倒されたと喜んでいました。「クラゲ館」のテーマは「いのちを高める」だそうです。来年万博でどのようなセネガルの映像が流れるのか楽しみです。
2 大使館からのお知らせ
○2024年9月、10月の休館日のお知らせ
9月16日 ※モハメッド誕生日
10月の祝日による休館日はありません。
※当初9月17日に予定されていましたが、セネガルの都合により9月16日に変更となりました。
3 寄稿 ~君島 崇 JICA農業専門家、(株)レックス・インターナショナル 代表取締役社長~
(1)はじめに
私はこれまで40年に亘り、世界の発展途上国における農業・農村開発や地域開発に関わる調査・計画立案、技術移転等、ODA(政府開発援助)業務に従事してきました開発コンサルタントです。業務で訪問した国は全世界で40を越える程度ですが、最近の20年はアフリカ地域でのコメ生産振興に関わる技術協力に特化した業務を行っており、その対象は西アフリカのセネガルとシエラレオネの二か国に集中しています。今回は長い付き合いになったセネガルの稲作と私の仕事に関する話をさせていただきます。
(2)セネガルと出会うきっかけとなったマスタープラン調査とコメ
セネガルとの付き合いは2004年、今から20年前に始まりました。大学の先輩であるコンサルタントの方にお声がけ頂き、JICAの調査案件に参加したのがきっかけでした。この調査は、セネガル全国を対象として、コメセクターの現状と課題を整理し、今後10年間の当セクター開発にかかるマスタープランを作成することが目的でした。調査期間は約2年間で、8名の日本人専門家が従事し、私は稲作栽培技術と社会経済面を担当しました。
当時のセネガルのコメセクターは、世界銀行による構造調整政策に基づき、1994年の通貨切り下げ、それまで生産から加工・流通までを支えてきた国営企業の解体などにより、混乱の真っ只中にありました。輸入機械や肥料は通貨切り下げの影響で価格が2倍になってしまい、生産費を大きく押し上げました。一方、国営企業の解体により流通経路を絶たれ、生産者はコメを作っても売り先がありません。特に、灌漑施設が整備されたセネガル川流域で、生業として稲作を行っていた農民組織にとっては、作ったコメが売れないのは死活問題でした。現場で「自分達の作ったコメを売れるようにして欲しい」という稲作農民の切実な声を聞いた、当時のJICAセネガル事務所長がこの調査案件を形成されたと聞いています。
(3)マスタープランのインパクトと日本のセネガルコメセクターへの貢献
このマスタープラン調査の結果、セネガルの国産米を売れるようにするためには、流通経路の確保もさることながら、消費者の嗜好に合った精米品質の向上が最重要課題であることがわかりました。ダカールを始めとする都会の消費者は、小石を含む不純物が多く混入し、くすんだ色の国産米を避け、輸入米を好んで食べていたのです。精米品質が向上して初めて、稲作農家は安心してコメを生産することができます。今後の稲作開発の優先順位と方向性が示されました。その後JICAは、このマスタープラン結果に基づき、生産ポテンシャルの高い北部セネガル川流域の灌漑地区のコメ生産性向上を目指す技術協力を実施し、その中で日本製の精米選別機を精米業者に導入したところ、国産米の精米品質が飛躍的に向上しました。その結果、セネガル川流域で生産されたコメ(国産米)が初めて、首都ダカールのスーパー店頭にも並ぶようになりました。
これは、セネガルの国家政策でもあるコメ自給計画の達成に向けた、日本の非常に大きな貢献でした。国産米が売れることが解り、農家は生産に集中することができるようになりました。
(4)セネガルの稲作の多様性
一方、この調査を通じ、セネガルのコメの生産環境は、自然条件、社会文化的背景、稲作の担い手等、地域により大きく異なることがわかりました。そのいくつかを紹介しましょう。
コメの生産地は主に、北部のセネガル川流域、中部のシン・サルム川流域及び南東部のガンビア川流域、そして、南部のカザマンス地域に分かれます。
セネガル川流域は、サハラ砂漠の南縁に近く、雨量は年間200~400mm程度のところが多く、農業は主に、ドナーの支援を受けてセネガル川沿いに建設された灌漑施設によって、水の制御が可能な環境で行われています。この地域は、稲の生育に適する粘土質土壌が分布し、また日射量が非常に大きいので、高投入により生産性の高い稲作が可能です。稲作の歴史は比較的浅く、稲作を担っているのは、下流域ではウォロフの人が多いのですが、内陸に行くに従い、元来遊牧民であるプルの人たちがほとんどです。
中部のシン・サルム川流域及び南東部のガンビア川流域では、農業は圧倒的に畑地で行われています。雨量も少ないことから、主食は男性が生産するミレットやトウモロコシが主体です。限られた低地で小規模に行われる稲作は、耕起作業から収穫・収穫後処理までを女性たちが担っており、主に自給用の稲作が行われています。男性に比べ、宗教的、社会文化的に地位の低い女性たちは情報や技術へのアクセスが限られており、伝統的な農法を親の代から受け継ぎ、農作業のほとんど全てを手作業で行っています。家事や子供の世話も彼女等の仕事で、寝る間も惜しんで働いています。稲作は南に隣接するガンビアあるいはさらに南のカザマンスから移住してきた人によって伝えられたと言われています。
一方、南部のカザマンス地域では、居住する民族によって稲作方法が異なっており、最も古くから稲作を行っていると言われるジガンショール州では、ジョラの人たちによるコメを中心とする文化が根付いています。耕起作業はカジャンドゥと呼ばれる船の櫂のような形をした、柄の長い特殊な鍬を用いて男性が行います。そして女性たちは苗代を作り、苗を育て、男性たちが耕し、畝立てた場所に移植をしていきます。ここでは、雑草は滅多に生えないので、除草はほとんどしないそうです。収穫はナイフを用いて穂の基部を切り取り、切り取った穂を束ねて、頭の上に載せて運びます。彼らにとって、コメは神聖な供え物として、冠婚葬祭に利用され、それためか、稲作には一切の化学物質や機械を使用しない地域が未だにあるそうです。また、ある家族の長が亡くなった時、家に蓄えているコメの量で、その長の偉大さを示すとのことです。さらには、食べるのに困った人たちを助けるため、支援用のコメを常時確保しているという話もあります。
このように、セネガルの中でも非常に多様な稲作を見ることができます。
(5)私の技術移転の方法
私は、上記マスタープラン調査以後、幸運にもセネガルで稲作振興に関わる技術協力プロジェクト4案件に関わる機会を得、北部、中部、南東部において、稲作を実践する農家及び彼らを指導する普及員たちと共に、稲生産性向上のための技術を開発し、それを普及する仕事をしてきました。技術開発とは言っても難しいものではなく、農民が実践している農作業をより効率的・効果的にするため、稲の生育時期に応じて、適時に適用させるものです。
稲のことは私の方が知っていることが多いのですが、気候や土壌の性質など、現地の環境の理解は地元の農民には叶いません。一見不適切だと思っても、彼らが実践する農作業にはそれなりの合理性があり、それを理解せずに、こちらの理論だけを押しつけても、それは受け入れられませんし、失敗します。まず、彼らが行う稲作と稲作を取り巻く環境を学び、その上で課題を整理し、課題解決へのアプローチについて幾通りもの道筋を考え、それらを農民たちに説明しつつ、試行錯誤する過程が必要になります。成果が見えるまでに時間がかかることもありますが、これが最も確実な方法だと信じて行っています。また、この過程を通じ、農民との信頼関係も構築されます。
(6)これまでの成果、現在、そして今後について
これまで関わった北部と中部での技術協力プロジェクトでは、開発した推奨技術の有効性が確認され、技術を移転された稲作農家は飛躍的に生産性を伸ばしました。
現在は南東部で、自然環境と稲作の担い手が異なる、多様な環境において、天水稲作生産性向上に挑戦しています。課題のキーワードを並べると、適正品種、陸稲栽培、雑草管理、除草剤、適正播種量、水管理、土壌保全、適正な農業機械、ジェンダー等、非常に多いことが解ります。それぞれの課題について、その解決は容易ではありませんが、協力農家や農民グループの稲作圃場を彼らと一緒に回りながら、稲の生育を見て、試した農作業や技術について、彼らと意見を交換しているところです。
また今後は、現在の南東部での業務と並行して、セネガルで最も早く稲作が始まったと言われている、南部カザマンス地域の稲作支援を行う予定です。北部の灌漑稲作から始まり、20年を経てやっと南部の天水稲作地帯、セネガルの稲の聖地に辿り着きました。
私は業務を通じて、セネガルの人々の生活や文化に接し、セネガル人の優しさ、明るさ、おおらかさに触れ、いつの間にか、すっかりセネガルのファンになっていました。以前、セネガル人の友人から「君島、老いは年齢ではなく、気持の問題だ」と言われ、腑に落ちたことがありました。もういつ引退しても良い年齢になりましたが、気持を若く保ち、セネガルのために自分ができることをもう少し続けたいと考えています。
4 領事便り
○ 在留邦人数の調査について
外務省は、毎年、海外にお住まいの在留邦人数を調査しています。
調査の対象となった方を対象に、9月1日以降に以下の件名のメールが配信されますので内容をご確認のうえ、同メールに記載の方法にて滞在期間の延長、帰国、転出手続きをお願いいたします。
メール件名:【外務省からのお知らせ】在留状況を確認しています。
対象者:1)在留届に登録されている全員または一部の方の滞在期間が超過している方
2)滞在期間が未登録の方
在留邦人の実態数調査にご協力よろしくお願いいたします。
5 政治・経済
○TICAD閣僚会合の開催
8月24-25日、東京でアフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合が開催されました。セネガルからはファル・アフリカ統合外務大臣が出席しました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/af/af1/pagew_000001_00583.html
https://x.com/MiaaeSenegal/status/1827749666622156927
○伊澤大使によるジュフ漁業・海洋・港湾インフラ大臣表敬
8月29日、伊澤大使はジュフ漁業・海洋・港湾インフラ大臣を表敬訪問し、水産分野における経済協力について意見交換を行いました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01511.html
○伊澤大使によるジョップ産業・通商大臣表敬
8月29日、伊澤大使は、ジョップ産業・通商大臣を表敬し、セネガルの産業化に向けた方策や来年セネガルが参加する2025年日本国際博覧会について意見交換を行いました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01509.html
○セネガル産業・通商大戦略会議の開催
9月19-20日にダカールにて「セネガル産業・通商大戦略会議」が開催されます。同会議は、セネガル産業の詳細な分析を共有し、新しい産業政策に関する意見交換と提案収集を行う重要な場となります。会議には、産業界のすべての関係者が集まり、セネガルの産業発展に向けた強い政治的コミットメントが示される予定です。
本イベントの開催時間や場所、アジェンダ等の詳細な情報について産業・通商省に問い合わせ中です。情報が入手でき次第、改めてご案内させていただきます。
この機会に、セネガル市場の将来の展望を理解し、貴社のビジネス戦略に役立てていただければと考えておりますので、日本企業の皆様は参加をご検討ください。
○「JICA Networking Fair Autumn 2024」 参加企業・団体募集
JICA留学生のインターンシップ受け入れ・採用やビジネス連携にご関心のある日本企業・団体を対象に、JICA留学生と日本企業・団体の企業交流会が以下のとおり開催されます。ご関心のある企業様は、参加をご検討ください。
開催日: 2024年10月4日(金)10:00~17:00
主催: JICA
場所:神戸サンボーホール
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000397.000074396.html
○JETROアフリカビジネスデスク
ジェトロ(日本貿易振興機構)は、アフリカでの事業展開を目指す法人及びアフリカですでに事業を展開している法人を対象に相談サービスを提供しています。
対象国は20か国で、セネガルも対象国に含まれていますので、活用をご検討ください。
【詳細】
https://www.jetro.go.jp/services/africa_bizdesk.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3vePD6Ntz0xjeO_a3yCxw3b_An2F6r7apxSQiUKG-mzCYiKcNYm7xnQmc_aem_fgnxm1eyZLBAn6WZF5me2A
○当館が所掌する4か国(セネガル、カーボベルデ、ガンビア、ギニアビサウ)の政治経済関連の一般情報は、毎月上旬に当館のHP「セネガル基礎情報」及び「新着情報」に「在セネガル大使館月例報告」として掲載しております。ご関心のある方は以下のリンクをご参照ください。
(参考)月例報告:https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01078.html
6 広報・文化便り
○京都精華大学のセネガル研修
当館は京都精華大学の夏の研修プログラムでセネガルを訪問中の学生らを迎え、日セネガルの大学間交流について意見交換しました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LAXGca8kcuVkx3GMPTe1aKJd5M4Hn94uU6kTRvxiMWbdK1zZiG8DvgQMzwiTP584l&id=100078921276471
○当館では、日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本関連行事のほか、知り合いの方のご活動等についての情報を( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )までお知らせください。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。当館HPやSNSへの掲載は随時行います。
○当館SNSでは、セネガルで開催されるイベントの告知や当館の活動報告を行っています。他にもたくさんのコンテンツがありますので、定期的にアクセスしてみてください。また、日・セネガル関係強化のため、ご関心のある投稿のRTやシェア等、皆さまのご協力をぜひお願いいたします。
TW:https://twitter.com/JapanEmbSenegal
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471
Instagram:https://www.instagram.com/japanembsenegal/
----------------------------------------------------------------------
[在セネガル日本大使館メールマガジン]
○本メールマガジンに関するご意見・ご要望は以下のメールアドレスあてに送信してください。新規配信登録のご希望もこちらまでお寄せください。
( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )
○参考ホームページ
首相官邸ホームページ ( www.kantei.go.jp )
外務省ホームページ ( www.mofa.go.jp/mofaj/ )
当館ホームページ ( https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
○発行:在セネガル日本大使館
Ambassade du Japon au Senegal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Senegal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55
◆ 目次 ◆
1 「伊澤修駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「寄稿文」
4 「領事便り」
5 「政治・経済」
6 「広報・文化便り」
***********************
1 伊澤修駐セネガル日本大使挨拶
8月は雲が多く時々スコールのような雨が降りますが、梅雨のように何日も雨が続くようなことは無く、街中の冠水も幸い2年前の洪水のように深刻ではありません。暑さも東京の暑さに比べるとそれ程でも無いと感じます。皆様如何お過ごしでしょうか。
昨年10月号の挨拶でも述べた通り、カザマンス地方には多くの残置地雷があり地域の復興の足かせとなっています。日本政府は残置地雷の除去に向けた協力を積極的に進めることとし、7月に本使は地雷除去のための特殊ブルドーザー2台等の資機材を供与する無償資金協力についての交換公文に署名をしました。日本企業がこの特殊ブルドーザーを開発しており、この日本の技術がカザマンス地方の地雷除去のために役立つことになります。また、これに併せて8月に自衛隊のOB等が組織するJMASというNGOがカザマンス地方を視察し、退役した元陸上自衛官による地雷除去作業への協力の可能性を検討することになりました。このように我が国は人的協力、物資協力の両面から地雷除去に全面的に協力することになります。
8月の後半から京都精華大学の学生達がフィールドワークのために当地を訪問しています。セネガルにおけるこの研究ツアーは2年前から始まっていて毎年夏に学生達が来るのですが、本使が学生達をお迎えするのはこれで3回目になります。因みに京都精華大学は日本の大学で始めてアニメ学部を設けた大学で、本使もサコ前精華大学学長等からセネガルにおける日本の漫画やアニメを通じた交流の進め方についてアドバイスを頂いています。日本では知られていませんが、セネガルを含め西アフリカは言語、宗教、社会慣習等、社会的文化的に大きな特徴があり研究対象として面白い地域だと思います。今回の学生達の訪問もそうですが、この西アフリカ地域に関心をもつ研究者、そして日本人が増えることを期待しつつお迎えしています。
9月4日より、古屋元セネガル大使の奥様で「手を洗おう会」の代表である古屋典子様がセネガルを訪問しています。典子様にとって久しぶりのセネガル訪問のようですが、今回は「手を洗おう会」の活動の一環で、孫の翠さんが作成した日仏ウォルフ語で書かれた「ディガンテ」という絵本をセネガルの子供達のために持ってきてくださいました。日本人としては母国語である日本語で学校教育を受けることは当たり前のように感じますが、セネガルでは学校教育において多くのセネガル人の言葉であるウォルフ語と仏語をどのように使って教育を進めていくか議論があります。典子様は母国語による教育が重要だと考えていて翠さんとともにこのような絵本を作られたそうです。
言葉と言えば、先日、慶応大学3年生の巴山未麗さんがセネガルに来ました。彼女はセネガルの子供達がしっかりと教育を受けるためには仏語の理解が必要だと考えていて、子供達向けにウォルフ語から仏語を学ぶためのアプリの作成を進めています。まだ若い学生さんがこのような試みを始めていることに本使は心から感心しています。遊びほうけていた遠い昔の自分の学生時代を反省しつつ、今の日本の若者はなかなかやるもんだと思い応援しています。
最後に、9月初めに来年の大阪万博のプロデューサーの一人で「クラゲバンド」のリーダーの中島さちこさんがバンドの皆さんと読売TVの撮影チームと共にセネガルに来ました。万博の「クラゲ館」で放映される映像を撮影するために訪問したそうです。撮影はゴレ島、ダカール市内、ンブールで行われ、特にゴレ島でクラゲバンドはンジャイローズ・ファミリーと一緒に演奏を行いました。ピアニストの中島さんは、6月のゴレ島平和音楽祭の際に寄贈され、現在ゴレ市の文化会館に保管されているピアノを楽しそうに弾いていました。視察や演奏を通じて中島さんはセネガルの雰囲気に圧倒されたと喜んでいました。「クラゲ館」のテーマは「いのちを高める」だそうです。来年万博でどのようなセネガルの映像が流れるのか楽しみです。
2 大使館からのお知らせ
○2024年9月、10月の休館日のお知らせ
9月16日 ※モハメッド誕生日
10月の祝日による休館日はありません。
※当初9月17日に予定されていましたが、セネガルの都合により9月16日に変更となりました。
3 寄稿 ~君島 崇 JICA農業専門家、(株)レックス・インターナショナル 代表取締役社長~
(1)はじめに
私はこれまで40年に亘り、世界の発展途上国における農業・農村開発や地域開発に関わる調査・計画立案、技術移転等、ODA(政府開発援助)業務に従事してきました開発コンサルタントです。業務で訪問した国は全世界で40を越える程度ですが、最近の20年はアフリカ地域でのコメ生産振興に関わる技術協力に特化した業務を行っており、その対象は西アフリカのセネガルとシエラレオネの二か国に集中しています。今回は長い付き合いになったセネガルの稲作と私の仕事に関する話をさせていただきます。
(2)セネガルと出会うきっかけとなったマスタープラン調査とコメ
セネガルとの付き合いは2004年、今から20年前に始まりました。大学の先輩であるコンサルタントの方にお声がけ頂き、JICAの調査案件に参加したのがきっかけでした。この調査は、セネガル全国を対象として、コメセクターの現状と課題を整理し、今後10年間の当セクター開発にかかるマスタープランを作成することが目的でした。調査期間は約2年間で、8名の日本人専門家が従事し、私は稲作栽培技術と社会経済面を担当しました。
当時のセネガルのコメセクターは、世界銀行による構造調整政策に基づき、1994年の通貨切り下げ、それまで生産から加工・流通までを支えてきた国営企業の解体などにより、混乱の真っ只中にありました。輸入機械や肥料は通貨切り下げの影響で価格が2倍になってしまい、生産費を大きく押し上げました。一方、国営企業の解体により流通経路を絶たれ、生産者はコメを作っても売り先がありません。特に、灌漑施設が整備されたセネガル川流域で、生業として稲作を行っていた農民組織にとっては、作ったコメが売れないのは死活問題でした。現場で「自分達の作ったコメを売れるようにして欲しい」という稲作農民の切実な声を聞いた、当時のJICAセネガル事務所長がこの調査案件を形成されたと聞いています。
(3)マスタープランのインパクトと日本のセネガルコメセクターへの貢献
このマスタープラン調査の結果、セネガルの国産米を売れるようにするためには、流通経路の確保もさることながら、消費者の嗜好に合った精米品質の向上が最重要課題であることがわかりました。ダカールを始めとする都会の消費者は、小石を含む不純物が多く混入し、くすんだ色の国産米を避け、輸入米を好んで食べていたのです。精米品質が向上して初めて、稲作農家は安心してコメを生産することができます。今後の稲作開発の優先順位と方向性が示されました。その後JICAは、このマスタープラン結果に基づき、生産ポテンシャルの高い北部セネガル川流域の灌漑地区のコメ生産性向上を目指す技術協力を実施し、その中で日本製の精米選別機を精米業者に導入したところ、国産米の精米品質が飛躍的に向上しました。その結果、セネガル川流域で生産されたコメ(国産米)が初めて、首都ダカールのスーパー店頭にも並ぶようになりました。
これは、セネガルの国家政策でもあるコメ自給計画の達成に向けた、日本の非常に大きな貢献でした。国産米が売れることが解り、農家は生産に集中することができるようになりました。
(4)セネガルの稲作の多様性
一方、この調査を通じ、セネガルのコメの生産環境は、自然条件、社会文化的背景、稲作の担い手等、地域により大きく異なることがわかりました。そのいくつかを紹介しましょう。
コメの生産地は主に、北部のセネガル川流域、中部のシン・サルム川流域及び南東部のガンビア川流域、そして、南部のカザマンス地域に分かれます。
セネガル川流域は、サハラ砂漠の南縁に近く、雨量は年間200~400mm程度のところが多く、農業は主に、ドナーの支援を受けてセネガル川沿いに建設された灌漑施設によって、水の制御が可能な環境で行われています。この地域は、稲の生育に適する粘土質土壌が分布し、また日射量が非常に大きいので、高投入により生産性の高い稲作が可能です。稲作の歴史は比較的浅く、稲作を担っているのは、下流域ではウォロフの人が多いのですが、内陸に行くに従い、元来遊牧民であるプルの人たちがほとんどです。
中部のシン・サルム川流域及び南東部のガンビア川流域では、農業は圧倒的に畑地で行われています。雨量も少ないことから、主食は男性が生産するミレットやトウモロコシが主体です。限られた低地で小規模に行われる稲作は、耕起作業から収穫・収穫後処理までを女性たちが担っており、主に自給用の稲作が行われています。男性に比べ、宗教的、社会文化的に地位の低い女性たちは情報や技術へのアクセスが限られており、伝統的な農法を親の代から受け継ぎ、農作業のほとんど全てを手作業で行っています。家事や子供の世話も彼女等の仕事で、寝る間も惜しんで働いています。稲作は南に隣接するガンビアあるいはさらに南のカザマンスから移住してきた人によって伝えられたと言われています。
一方、南部のカザマンス地域では、居住する民族によって稲作方法が異なっており、最も古くから稲作を行っていると言われるジガンショール州では、ジョラの人たちによるコメを中心とする文化が根付いています。耕起作業はカジャンドゥと呼ばれる船の櫂のような形をした、柄の長い特殊な鍬を用いて男性が行います。そして女性たちは苗代を作り、苗を育て、男性たちが耕し、畝立てた場所に移植をしていきます。ここでは、雑草は滅多に生えないので、除草はほとんどしないそうです。収穫はナイフを用いて穂の基部を切り取り、切り取った穂を束ねて、頭の上に載せて運びます。彼らにとって、コメは神聖な供え物として、冠婚葬祭に利用され、それためか、稲作には一切の化学物質や機械を使用しない地域が未だにあるそうです。また、ある家族の長が亡くなった時、家に蓄えているコメの量で、その長の偉大さを示すとのことです。さらには、食べるのに困った人たちを助けるため、支援用のコメを常時確保しているという話もあります。
このように、セネガルの中でも非常に多様な稲作を見ることができます。
(5)私の技術移転の方法
私は、上記マスタープラン調査以後、幸運にもセネガルで稲作振興に関わる技術協力プロジェクト4案件に関わる機会を得、北部、中部、南東部において、稲作を実践する農家及び彼らを指導する普及員たちと共に、稲生産性向上のための技術を開発し、それを普及する仕事をしてきました。技術開発とは言っても難しいものではなく、農民が実践している農作業をより効率的・効果的にするため、稲の生育時期に応じて、適時に適用させるものです。
稲のことは私の方が知っていることが多いのですが、気候や土壌の性質など、現地の環境の理解は地元の農民には叶いません。一見不適切だと思っても、彼らが実践する農作業にはそれなりの合理性があり、それを理解せずに、こちらの理論だけを押しつけても、それは受け入れられませんし、失敗します。まず、彼らが行う稲作と稲作を取り巻く環境を学び、その上で課題を整理し、課題解決へのアプローチについて幾通りもの道筋を考え、それらを農民たちに説明しつつ、試行錯誤する過程が必要になります。成果が見えるまでに時間がかかることもありますが、これが最も確実な方法だと信じて行っています。また、この過程を通じ、農民との信頼関係も構築されます。
(6)これまでの成果、現在、そして今後について
これまで関わった北部と中部での技術協力プロジェクトでは、開発した推奨技術の有効性が確認され、技術を移転された稲作農家は飛躍的に生産性を伸ばしました。
現在は南東部で、自然環境と稲作の担い手が異なる、多様な環境において、天水稲作生産性向上に挑戦しています。課題のキーワードを並べると、適正品種、陸稲栽培、雑草管理、除草剤、適正播種量、水管理、土壌保全、適正な農業機械、ジェンダー等、非常に多いことが解ります。それぞれの課題について、その解決は容易ではありませんが、協力農家や農民グループの稲作圃場を彼らと一緒に回りながら、稲の生育を見て、試した農作業や技術について、彼らと意見を交換しているところです。
また今後は、現在の南東部での業務と並行して、セネガルで最も早く稲作が始まったと言われている、南部カザマンス地域の稲作支援を行う予定です。北部の灌漑稲作から始まり、20年を経てやっと南部の天水稲作地帯、セネガルの稲の聖地に辿り着きました。
私は業務を通じて、セネガルの人々の生活や文化に接し、セネガル人の優しさ、明るさ、おおらかさに触れ、いつの間にか、すっかりセネガルのファンになっていました。以前、セネガル人の友人から「君島、老いは年齢ではなく、気持の問題だ」と言われ、腑に落ちたことがありました。もういつ引退しても良い年齢になりましたが、気持を若く保ち、セネガルのために自分ができることをもう少し続けたいと考えています。
4 領事便り
○ 在留邦人数の調査について
外務省は、毎年、海外にお住まいの在留邦人数を調査しています。
調査の対象となった方を対象に、9月1日以降に以下の件名のメールが配信されますので内容をご確認のうえ、同メールに記載の方法にて滞在期間の延長、帰国、転出手続きをお願いいたします。
メール件名:【外務省からのお知らせ】在留状況を確認しています。
対象者:1)在留届に登録されている全員または一部の方の滞在期間が超過している方
2)滞在期間が未登録の方
在留邦人の実態数調査にご協力よろしくお願いいたします。
5 政治・経済
○TICAD閣僚会合の開催
8月24-25日、東京でアフリカ開発会議(TICAD)閣僚会合が開催されました。セネガルからはファル・アフリカ統合外務大臣が出席しました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/af/af1/pagew_000001_00583.html
https://x.com/MiaaeSenegal/status/1827749666622156927
○伊澤大使によるジュフ漁業・海洋・港湾インフラ大臣表敬
8月29日、伊澤大使はジュフ漁業・海洋・港湾インフラ大臣を表敬訪問し、水産分野における経済協力について意見交換を行いました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01511.html
○伊澤大使によるジョップ産業・通商大臣表敬
8月29日、伊澤大使は、ジョップ産業・通商大臣を表敬し、セネガルの産業化に向けた方策や来年セネガルが参加する2025年日本国際博覧会について意見交換を行いました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01509.html
○セネガル産業・通商大戦略会議の開催
9月19-20日にダカールにて「セネガル産業・通商大戦略会議」が開催されます。同会議は、セネガル産業の詳細な分析を共有し、新しい産業政策に関する意見交換と提案収集を行う重要な場となります。会議には、産業界のすべての関係者が集まり、セネガルの産業発展に向けた強い政治的コミットメントが示される予定です。
本イベントの開催時間や場所、アジェンダ等の詳細な情報について産業・通商省に問い合わせ中です。情報が入手でき次第、改めてご案内させていただきます。
この機会に、セネガル市場の将来の展望を理解し、貴社のビジネス戦略に役立てていただければと考えておりますので、日本企業の皆様は参加をご検討ください。
○「JICA Networking Fair Autumn 2024」 参加企業・団体募集
JICA留学生のインターンシップ受け入れ・採用やビジネス連携にご関心のある日本企業・団体を対象に、JICA留学生と日本企業・団体の企業交流会が以下のとおり開催されます。ご関心のある企業様は、参加をご検討ください。
開催日: 2024年10月4日(金)10:00~17:00
主催: JICA
場所:神戸サンボーホール
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000397.000074396.html
○JETROアフリカビジネスデスク
ジェトロ(日本貿易振興機構)は、アフリカでの事業展開を目指す法人及びアフリカですでに事業を展開している法人を対象に相談サービスを提供しています。
対象国は20か国で、セネガルも対象国に含まれていますので、活用をご検討ください。
【詳細】
https://www.jetro.go.jp/services/africa_bizdesk.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3vePD6Ntz0xjeO_a3yCxw3b_An2F6r7apxSQiUKG-mzCYiKcNYm7xnQmc_aem_fgnxm1eyZLBAn6WZF5me2A
○当館が所掌する4か国(セネガル、カーボベルデ、ガンビア、ギニアビサウ)の政治経済関連の一般情報は、毎月上旬に当館のHP「セネガル基礎情報」及び「新着情報」に「在セネガル大使館月例報告」として掲載しております。ご関心のある方は以下のリンクをご参照ください。
(参考)月例報告:https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01078.html
6 広報・文化便り
○京都精華大学のセネガル研修
当館は京都精華大学の夏の研修プログラムでセネガルを訪問中の学生らを迎え、日セネガルの大学間交流について意見交換しました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LAXGca8kcuVkx3GMPTe1aKJd5M4Hn94uU6kTRvxiMWbdK1zZiG8DvgQMzwiTP584l&id=100078921276471
○当館では、日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本関連行事のほか、知り合いの方のご活動等についての情報を( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )までお知らせください。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。当館HPやSNSへの掲載は随時行います。
○当館SNSでは、セネガルで開催されるイベントの告知や当館の活動報告を行っています。他にもたくさんのコンテンツがありますので、定期的にアクセスしてみてください。また、日・セネガル関係強化のため、ご関心のある投稿のRTやシェア等、皆さまのご協力をぜひお願いいたします。
TW:https://twitter.com/JapanEmbSenegal
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471
Instagram:https://www.instagram.com/japanembsenegal/
----------------------------------------------------------------------
[在セネガル日本大使館メールマガジン]
○本メールマガジンに関するご意見・ご要望は以下のメールアドレスあてに送信してください。新規配信登録のご希望もこちらまでお寄せください。
( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )
○参考ホームページ
首相官邸ホームページ ( www.kantei.go.jp )
外務省ホームページ ( www.mofa.go.jp/mofaj/ )
当館ホームページ ( https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
○発行:在セネガル日本大使館
Ambassade du Japon au Senegal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Senegal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55