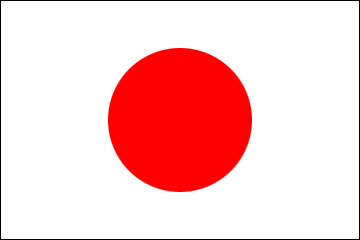メールマガジン10月号
令和4年10月12日
皆様、如何お過ごしでしょうか。
本使は、先月後半から休暇で日本に帰国しています。健康管理の目的の休暇ではありますが、せっかくの機会なので日セネガル関係に縁のある方々やその発展にご協力頂ける方々を中心にアポや意見交換を精力的にこなしています。日セネガル関係に関与する方々は、経済協力やビジネスといった経済関係、政治・地域情勢といった政治関係、文化交流や学生等の交流等、幅広い分野で活躍されているので、本使がお会いする方々も様々です。更に、まだ皆様に具体的にお伝えできないのですが、これまでセネガルでは活動がみられなかった分野での日本の協力についても働きかけを行っています。本使は今週末セネガルに戻りますが大変実り多い休暇でした。「実り多い休暇」というのは若干矛盾しているようにも思えますが、休むことが苦手な本使ですので、まあいいでしょう。今回皆様への報告としては、シス在京セネガル大使やサコ京都精華大学前学長にこのメールマガジンへの寄稿に賛同して頂きました。追って掲載させて頂きます。
本使は今回の帰国でお会いした方々に一つの見方を伝えてきました。
確かに今日アフリカでは、中国、欧米やロシア等の大国の動きが活発であり、特にセネガルでは伝統的な仏に加えて資金力を背景に中国やトルコの活動が目覚ましいものがある。その結果アフリカにおいて日本の影響力が下がっていると懸念する向きもある。確かに中国はかなりの資金をアフリカに投じている。しかしながら、その一方で、アフリカの多くの国々は地下資源を有しない国がほとんどである。日本は、地下資源を大して有していないにもかかわらず、明治時代から紆余曲折がありながらも発展を続け先進国になったことは、このような資源を有しない多くのアフリカ諸国にとって依然として目指すべき国のモデルなのではないか、いやモデルでありつづけるべきではないか?資源を有する中国や米国、植民地支配の苦い歴史のある欧州諸国、資源大国ロシア、このいずれをとっても彼らの目指すべき発展のモデルにはなりえない。人的資源に投資をして、人的資源を中心に国を発展させた日本こそが資源を有しないの多くのアフリカ諸国にとって引き続き目指すべき発展のモデルとしてあり続けるべきだろう。
本使は今週末セネガルに戻り、10月24日から始まるダカール・フォーラムの準備に取り掛かります。ウクライナでの戦争が世界情勢に大きな影響を与えていますが、セネガル周辺地域でも不安定な情勢が続いており、ここセネガルでこうした安全保障の問題をしっかり議論することは大変有意義なことだと思います。日本からは例年ハイレベルの政務に参加いただいています。本年も出張予定の政府の代表をお支えして、日本の声を国際社会に対してしっかり伝えていきたいと思います。
本使は、先月後半から休暇で日本に帰国しています。健康管理の目的の休暇ではありますが、せっかくの機会なので日セネガル関係に縁のある方々やその発展にご協力頂ける方々を中心にアポや意見交換を精力的にこなしています。日セネガル関係に関与する方々は、経済協力やビジネスといった経済関係、政治・地域情勢といった政治関係、文化交流や学生等の交流等、幅広い分野で活躍されているので、本使がお会いする方々も様々です。更に、まだ皆様に具体的にお伝えできないのですが、これまでセネガルでは活動がみられなかった分野での日本の協力についても働きかけを行っています。本使は今週末セネガルに戻りますが大変実り多い休暇でした。「実り多い休暇」というのは若干矛盾しているようにも思えますが、休むことが苦手な本使ですので、まあいいでしょう。今回皆様への報告としては、シス在京セネガル大使やサコ京都精華大学前学長にこのメールマガジンへの寄稿に賛同して頂きました。追って掲載させて頂きます。
本使は今回の帰国でお会いした方々に一つの見方を伝えてきました。
確かに今日アフリカでは、中国、欧米やロシア等の大国の動きが活発であり、特にセネガルでは伝統的な仏に加えて資金力を背景に中国やトルコの活動が目覚ましいものがある。その結果アフリカにおいて日本の影響力が下がっていると懸念する向きもある。確かに中国はかなりの資金をアフリカに投じている。しかしながら、その一方で、アフリカの多くの国々は地下資源を有しない国がほとんどである。日本は、地下資源を大して有していないにもかかわらず、明治時代から紆余曲折がありながらも発展を続け先進国になったことは、このような資源を有しない多くのアフリカ諸国にとって依然として目指すべき国のモデルなのではないか、いやモデルでありつづけるべきではないか?資源を有する中国や米国、植民地支配の苦い歴史のある欧州諸国、資源大国ロシア、このいずれをとっても彼らの目指すべき発展のモデルにはなりえない。人的資源に投資をして、人的資源を中心に国を発展させた日本こそが資源を有しないの多くのアフリカ諸国にとって引き続き目指すべき発展のモデルとしてあり続けるべきだろう。
本使は今週末セネガルに戻り、10月24日から始まるダカール・フォーラムの準備に取り掛かります。ウクライナでの戦争が世界情勢に大きな影響を与えていますが、セネガル周辺地域でも不安定な情勢が続いており、ここセネガルでこうした安全保障の問題をしっかり議論することは大変有意義なことだと思います。日本からは例年ハイレベルの政務に参加いただいています。本年も出張予定の政府の代表をお支えして、日本の声を国際社会に対してしっかり伝えていきたいと思います。