「文化を通じた平和」シンポジウム
5月13日,北原大使公邸にて,「文化を通じた平和」シンポジウムが開催されました。このシンポジウムは,平成27年6月に岸田外務大臣により日EU俳句交流大使を委嘱されたヘルマン・ファンロンパイ前欧州理事会議長により,俳句の文化的な意義,そして平和な世界の構築のために文化が果たす役割について語るとともに,セネガル政府要人であるペンダ・ンバウ大臣(仏語圏フォーラム・セネガル政府代表)をスピーカーに,また,女性法曹として女性の権利保護に積極的な活動を行っているファトゥ・キネ・カマラ氏(セネガル法律家協会会長)をモデレーターとして迎え,討論会及び質疑応答を行いました。
概要は以下のとおりです。
1 登壇者
(1)ヘルマン・ファンロンパイ 日EU俳句交流大使
(2)ペンダ・ンバウ 仏語圏フォーラム・セネガル政府代表
(3)ファトゥ・キネ・カマラ セネガル法律家協会会長
2 主な出席者
アワ・マリー・コル・セック保健・予防大臣,マンスール・シィ国民議会副議長,バカリィ・サンブゥ教授,イバ・デル・チャム元国民議会副議長他
3 シンポジウム概要
(1)冒頭 北原大使挨拶

来賓の皆様のご出席に感謝するとともに,ファンロンパイ日EU俳句交流大使のダカールへの来訪を心より歓迎する。
本日のシンポジウムは,ベルギー首相,初代EU大統領を歴任される傍ら,俳人として著作を出版し俳句の普及に尽力された功績から,2015年6月に岸田外務大臣より「日EU俳句交流大使」を委嘱されたファンロンパイ氏,そして,イスラム及び西欧における中世の歴史家としてシェーク・アンタ・ジョップ大学にて教鞭を執られ,仏語圏フォーラム・セネガル政府代表を務められたペンダ・ンバウ氏,また,セネガルにおける女性の地位向上に尽力されている法学博士のカマラ氏をお迎えして,現在,世界のあらゆる地域にて重要な問題である「文化を通じた平和」について討論する。
激しい戦火に見舞われた20世紀を経て,21世紀は知恵と平和の世紀であるよう万人が希求しているにもかかわらず,国際情勢は非情かつ無慈悲なテロリストの暴行に直面し,不安定な地域から欧州に向け移動する大規模な難民の発生等,困難を極めている。我々の課題は普遍的な価値である平和と繁栄の再生である。
こうした問題を解決に導くためには,途上国への開発支援が重要であることは言うまでもない。しかし,阻害された若者たちの社会への再統合,社会的格差の是正,教育,異なる宗教と文明への理解が必要となろう。
本日の登壇者はまさにこうしたテーマを討論するにふさわしい方々である。
TICADについて少し紹介させていただきたい。本年8月にナイロビにて,アフリカ大陸において初めての開催となるTICADⅥが予定されている。主要な議題はアフリカにおける開発であるが,「平和と安全保障」,そして文化についても討論が行われることであろう。本日の議論の成果を広く共有し,TICADⅥに向けて展開させていきたい。
(2)ファンロンパイ日EU俳句交流大使 講演
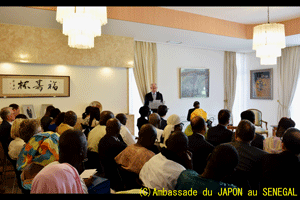
自分(ファンロンパイ俳句大使)は,2004年,偶然により俳句に出会った。俳句は,他の詩作と同じく,我々がその一部をなす自然における経験から生まれる。自然は万物の秩序である調和をも明らかにする。この調和が感情を動かし,あらゆる詩の源となる。
俳句の形式と内容はシンプルなものであり,はかなく小さな出来事や発見を甦らせ,普遍的な事象に表現する創作である。俳句の技巧とは,作品の最後の5音節でこの飛躍を生むことにある。単に描写するだけでなく,具体的な経験の背後や水面下に潜む世界を暗示させる言葉を見つけることである。俳句とは単なる句にあらず。それは「物の見方」であり「人生の道筋」である。
政治と俳句,また詩と俳句の関係とは何か。政治とは,権力への闘争,イデオロギー的な争いといった対立に基づいている。詩はしばしば内面の葛藤を伝えるものであり,個人的な冒険である。政治家にも多様な内面があり,俳句は人格の一部を成し,何ら相反するものはない。詩作は政治家にとってあらゆる的確な判断に必要とされる「距離を取る」方法をも与えるものである。
世界には引き続き不安定と恐怖と戦争のさなかにある地域が存在し,アフリカも同様である。欧州は戦争の数世紀を経て,「恒久平和」に向けた長い道のりを歩み,平和に資する目的として経済的相互依存の手段を選択した。アフリカ連合も地域における協力を模索し,近年大きな進展が認められるが,追求すべき道のりは続いている。過去の過ちに陥ってはならない。
アフリカの自然は,気候変動について効果的かつ決定的な方法にて解決されなければ,甚大な損害を被る可能性がある。欧州は,人類存命への闘いにおいて,アフリカの強力な仲間である。自然保護は詩作の保護でもある。このことを,アフリカの偉大な詩人であるサンゴール初代大統領の祖国であるセネガルにて述べておきたい。
世界のグローバル化は,詩作にも当てはまる。本日この地で,ひとりの欧州人がアフリカで,日本の文化遺産である俳句について話しており,3つの地域が詩作に関連して集っている。「美は世界を救うものではない」。しかし,手助けをすることは可能である。人間は,善意と美との自然の絆を深めることが可能である。
アフリカには「知恵は富を凌駕する」という美しいことわざがある。今日,非合理かつ好戦的な世界において,我々は知恵を必要としている。
俳句の創作は,古典詩作とは異なり,同人が集い,意見交換を行い,各人の句に筆を入れるところにその独自性がある。同人との共同作業はあまり知られていない側面ではあるが,俳句文化の一部を成すものである。俳句とはある民主主義の形である。民主主義とはひとつの対話である。現在では年齢を問わず多数の人々が俳句に親しんでおり,かように人々に開かれているという意味において,これほどまでに「民主的な」詩句の形式は他にはない。
我々は普遍的に,対話,美,そして平和を必要としている。希望はそれらの柱に基づいている。人類にも同じく必要である。詩句を通じて,希望の根拠を自らに与えようではないか。
(3)ペンダ・ンバウ 仏語圏フォーラム・セネガル政府代表 講演

西アフリカにおけるテロリズム及び過激派の増加について,問題の根源は,対話とコミュ二ケーションの場の欠如にある。
ユートピアは世界中に起こった幾多の戦争の結果誕生した。新しい文明の再建の希望もあったが,現在,我々は不幸にもそのプロセスの末期に存在している。世界は,テロリズムの増加により憂慮すべき状態にある。アンドレ・マルローは「21世紀は精神性の高い世紀となるか否か」と問うたが,この言葉を今日実証するのは困難である。宗教間の対話や宗教的寛容が欠如しているからである。人々は誤った解釈に基づいており,宗教は対話と平和の深化に寄与すべきであるにもかかわらず,今日,それは悲劇的な事件に集中してしまっている。ボコハラム等の勢力は,宗教は暴力的な結末の道具として用いられうると,我々に信じさせようとしている。
他にも問題の根底には,強制的に解決せられるべきであったイスラエル・パレスチナ紛争を例として,他のあらゆる紛争の原因である社会的不正の問題にある。
1979年のホメイニ師の即位は,政治化したイスラムの効果的な転換点であった。この政治化は,しかしながら,共同体をカオスに向かわせる権力の操作により周知されることとなった。為政者は次に,彼ら独自のイデオロギーを作り,強制できると考えた。しかし不幸なことに,彼らは不寛容と暴力を用いて和平を蒸し返しただけであった。
テロリズムは,確かに,制圧は難しい。しかし,国家はしっかりと関与するべきである。同様に,国連のシステムも再検討されるべきであろうし,国際的な懸念について責任を負う新しい機関の設立を検討すべきだろう。同時に,紛争は教育によってのみ解決できるが,この問題についても残念なことに,特にアフリカでは危機的な状況にある。
最後に,人類は平和と世界の安定のために,隣人に胸襟を開いて対話すべきである。
(4)モデレーターのファトゥ・キネ・カマラ氏を交えての討論

カマラ氏は,ファンロンパイ俳句大使の講演から詩作の重要性について触れ,国際的な平和構築に向けての詩人的政治家の存在について質し,詩作は我々に対し,ヒューマニズムと調和への希求をもたらすものであろうと述べた。これに対し,ファンロンパイ俳句大使は,現代社会は攻撃的かつ個人主義化の傾向にあり,その文脈からすると,俳句は新たな考え方の人間をつくる解毒剤のような役割となることも考えられる,また,常に希望への欲求をかき立てていくことが必要であり,何故なら希望とは社会を発展させるものであるからである,絶望した人間は絶望的な行動しかなしえないと述べた。
次にカマラ氏は,平和構築に必要な要素についてペンダ・ンバウ氏に質したところ,日本を例に挙げ,日本の文化が発展の基礎となった,人類は技術的な進歩を遂げたが,我々は皆,人間味のある部分に身を守る必要を感じている,人間は精神的なものがなくては生きていけないが,最も活発な集団はしばしば宗教的な集団である,大切なのは,多様な起源をもつ人々との対話の場を作ること,つまり,世界規模の対話が再構築されるべきであり,より前進するためには,故サンゴール大統領が推奨したように,世界におけるあらゆる文明を復興させることが必要,そのためには,教育が当然のごとく中心に置かれなければならない,と述べた。
(5)出席者からの発言
(イバ・デル・チャム元国民議会副議長)将来についてより適切に懸念するには,歴史と文化に帰ることである。我々アフリカ人は,自分たちを遅れていると考えるべきではない。何故なら,矛盾を超えるという決意に基づき,我々は国家間のコンサートの中に我々の居場所を見つけることが可能になるからである。最も大きな問題は,人間性というものは文化の公平性を認識しないことである。世界の全体化は文化の違いを無視するばかりでなく,アフリカを排除することにある。そもそも,世界銀行や国連といった機関は,常に彼らのラインを我々に命令するばかりである。こうして,残念なことに,我々が今日直面している暴力の源となるフラストレーションを生んだのである。しかし,自分は楽観主義を保ち,ユートピアと神話の保全を働きかけていきたい。
(マジュール・ジュフ俳句コンクール審査委員長)俳句は世界中にてもっと詠まれるべき詩作である。イスラエル・パレスチナ間の敵意は,共生への意欲の欠如である。文化の深化と開化を唯一保証するものとして,教育が重要である。
(マンスール・シィ国民議会副議長)宗教間の対立の解決は,それぞれの意見を議論し共有する場の創設に資する,本日のシンポジウムの精神に宿ると言っても過言ではない。
(バカリィ・サンブゥ教授)すべての紛争は,ごく少数のマイノリティを優遇し大多数の貧者を不利にするため,最終的には富と権力の不公平な再配分に帰着するだけである。それゆえ,西アフリカの公式な特色もないままフランスの教育システムとアラブの教育システムを導入している二重性にかんがみ,果たして教育が適切な解決策であると実証できるかという疑問が残る。
(ジョル・ファル・ソウ女史)発展を保証する文化と平和教育を語ることなしに,単に平和について語ることはできない。
(6) 登壇者による総括
今般の議論を総括し,キーワードは,尊重と開放を前提とした対話となろう。我々は今日,正義の欠如とも言うべき世界に存在しているが,被害者が過去についていつまでも反芻し続けるならば,解決策は無効になるおそれがある。例として,イスラエル・パレスチナ間の紛争に戻るとすると,欧州が行ったように許し歴史のページをめくる術を知る必要があろう。
人間としての文化には物事を進める力はあるが,制度としての対話と世界について再考する必要がある。社会と学校を通じた教育は確かに進歩するが,我々固有の文化と現実を組み立てる必要があろう。
文化的要素としてひとつ例を挙げると,俳句は日本文化の発展に貢献したと言える。
国民または民族間の,あるいは異なる文明間の和解をもたらす文化は,平和への序章を記すと言っても過言ではない。
シンポジウムのテーマに戻ると,結論として,文化がなければ平和構築はあり得ないと言えよう。今日のグローバリゼーションも文化の恩恵によるものであり,より厳密に言うと,他者の文化を否定することを禁じるよう留意しなければ,フラストレーションと暴力を招くばかりである。
暴力を阻止し,平和を達成するため,文化と平和との関係に着目した今回の討論でキーワードとなったのは「対話」であろう。ファンロンパイ俳句大使の言葉を引用すれば,「対話」が制度化され,寛容をもって浸透させなければならない。
結論として,人間性が平和を促進し熱望するのであれば,それ自身が歴史のページを繰り,世界を再検討するために必要とされるのである。






