経済協力詳細
1. セネガルの概要と開発課題
(1) 概要
セ ネガルは、 1960 年の独立以来、一度もクーデターを経験しておらず内政上高い安定を維持している。 1976 年に複数政党制を導入し、 2000 年 3 月の大統領選挙では平和裡に政権交代が行われた。また 2007 年の大統領選挙においても、ワッド大統領が大きな混乱もなく再選されるなど民主主義が定着している。

外交面では、穏健な現実路線外交を基本としており、旧宗主国のフランスをはじめ多くの先進国、アラブ、イスラム諸国と友好関係を築いており、2008年3月にはイスラム諸国会議機構(OIC) サミットをダカールで開催するなどプレゼンス強化を図っている。また、アフリカ連合(AU)にも積極的に関与し、アフリカ外交において重要な地位を占めている。

経済面では、1994年の域内通貨切り下げ、国営企業の民営化等、様々な構造改革を断行することによって、経済は成長基調に乗り、特に近年は民間投資の伸びや海外からの送金の増加も経済の成長を支えている。近年は平均5%台の高いGDP成長率を維持し、インフレ率も比較的低く抑制されるなど概ね順調なマクロ経済運営を遂げている。一方では積極的なインフラ整備の推進により財政赤字及び経常収支赤字が上昇する傾向にあり、今般の燃料価格、食糧価格高騰対策としての補助金支出増加による財政収支への影響が懸念材料となっている。
全人口に対する貧困人口の割合は1994年の68%から2005年には57%へと改善してきたものの、貧困人口の絶対数は増加している。また地方と都市の地域間格差、人口増加、都市部への流入、貧富の格差拡大、不法移民、砂漠化 等の問題を抱えており、セネガルは依然として脆弱な経済・社会・環境構造の上に立脚している。
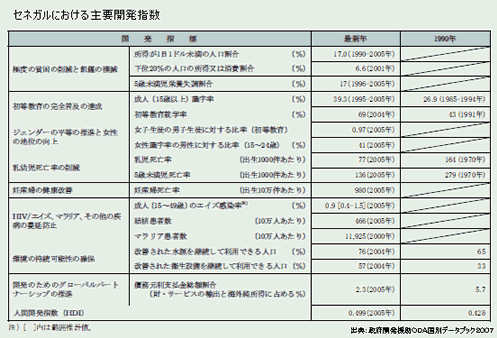
(2)貧困削減戦略文書( PRST Ⅱ)

セネガル政府は、2006年に改訂した第二次貧困削減戦略文書(PRSP Ⅱ:2006-2010年)において、貧困削減のための優先目標を設定し、
①「富の創出」、
②「基礎社会サービス」、
③「社会保護と災害予防と管理」、
④「グッドガバナンスと地方開発」
を4本の柱としている。特に「富の創出」に対して、セネガル政府は首相府主導で「経済成長戦略(SCA)」を打ち出し、経済成長を強く志向した経済開発を目指している。またワッド大統領はNEPAD案件策定にイニシアティブを発揮し、大規模な経済インフラ整備を提唱している。
セネガル政府及び開発パートナーの間では、PRSP/PRSPIIが開発戦略の基本的枠組みであるとの共通認識があり、これに整合する公共投資3ヵ年プログラム(PTIP)、環境、司法、教育、保健の4セクターにおける中期支出枠組み(MTEF)、各セクタープログラム等が策定されている。
2.セネガルに対するODAの考え方
(1)セネガルに対するODAの意義
セネガルは西アフリカの中心国の1つであると共に、域内及びAU内で重要な地位を占めており、TICADプロセスに積極的に参加し、クールアース・パートナーシップに賛同するなど我が国とは良好な関係を維持している。セネガルへの支援は、二国間の緊密な友好・協力関係を深化させるだけでなく、西部アフリカ地域全体の安定と発展に貢献することが期待出来ることから、我が国のODA大綱の「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄の確保に資すること」という理念にも合致し、その意義は大きい。さらに、世界銀行、IMFの支援の下、構造調整や経済改革に自立的かつ積極的に取り組むセネガルに対し、経済協力の基本である自助努力を促し、我が国としてODAにより支援することは、ODA 大綱の重点課題である「貧困撲滅」や「持続的成長」の観点からも意義は大きい。
(2)セネガルに対するODAの基本方針
セネガル政府は、PRSPの改訂やSCAの策定にみられるように、貧困削減を実現するにあたって、依然社会開発を重視しつつも、経済成長を強く志向する経済開発を目指している。我が国は、このようなセネガル政府の現状に鑑みながら国別援助計画、PRSPⅡ等のセネガルの開発計画を踏まえると共に、TICAD Ⅳにおいて採択された「横浜宣言」、フォローアップメカニズム等を念頭に置きつつ、「社会開発と経済開発のバランスのとれた国造り~社会開発を重視しつつ、持続的な経済成長を展望した(見据えた)支援~」との標題を大目標に設定し、まずは引き続き社会開発を重視した支援を実施しつつも徐々に持続可能な経 済開発における支援を拡充していくことを検討している。
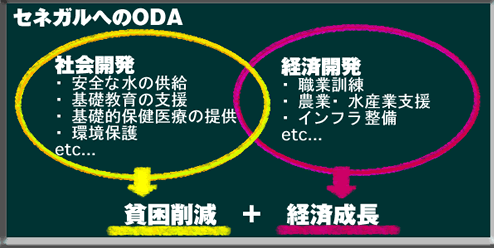
(3)重点分野
「社会開発と経済開発のバランスの取れた国造り」の実現を支援するために、我が国が重点を置いて支援すべき中目標として「地方村落における貧困層の生活改善」と「持続的な経済成長のための基盤造り」の2つを設定し、更に以下のとおり各中目標に2つの小目標を設定し、支援していく。
(イ)地方村落における貧困層の生活改善
「地方村落開発」及び「基礎社会サービスの向上」を小目標に据え、地域住民自らが基礎社会サービスの管理に参画し、地方村落における貧困削減に取り組み、急激な都市化の回避や地方村落から経済成長につながる環境づくりを目的とする社会開発を行う。
(ロ)持続的な経済成長のための基盤造り
「地場産業の振興とその基盤整備」と「産業人材育成」を小目標に据え、貧困層の雇用を創出し、所得向上をもたらす潜在力のある地場産業の振興、人材育成を行うとともに、村落から域内市場へのアクセス改善、インフラ基盤の整備に取り組む。
3. ODA実績
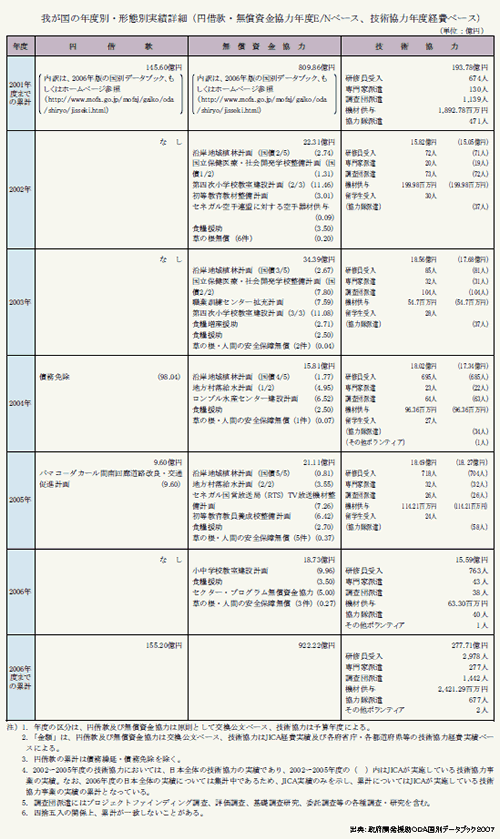
4. セネガルにおける援助協調の現状と我が国の関与

(1)数多くの他の開発パートナーもセネガルを西アフリカ地域の重点国として支援してきており、近年では、特にイスラム系開発機関、中国、インドや民間セクターなどの新興パートナーがプレゼンスを高めてきている。援助協調については、世銀、UNDPが共同議長として年2回開催される開発パートナー会合があり、カザマンス問題や教育、保健、給水等セクター別の会合が存在する。セネガル政府は基本的に国際社会からの援助が財政支援へ移行することを望んでおり、2007年に財政支援枠組合意文書が署名されたことを受けて、財政支援が動き出した。もっとも、従来のプロジェクト型 支援の有効性も認識されており、セクターによっては各ドナー間の援助協調が、情報交換のみならず共通ポジションを形成してセネガル政府に働きかけたり、セクター別の援助協調枠組み文書の作成に向けた取り組み等も行われている。さらに、市民社会等が重要な開発パートナーとして存在感を発揮している。
(2)そのような潮流を注視するためにも可能な限り現地の ODA タスクフォースメンバーが主要なドナー会合に参加するよう心掛けており、ドナー間での情報共有、意見交換等に努めている。
5. 留意点
(1)セネガルは、サブサハラ諸国の中では援助依存度が比較的低く自らの歳入努力が見られる国に位置づけられ、IMFのレポートでも債務は中長期的に返済可能であると判断されている。しかし、セネガル政府が積極的なインフラ整備を志向していることに伴い、今後、対外援助 を含む外国からの借入依存度及び財政赤字・経常収支赤字 が急上昇しないよう注視していく必要がある。
(2)ガバナンスについては、良好なレベルとされているが、予算・調達プロセスの改善や透明性・アカウンタビリティの向上などについて、セネガルの更なる自覚を促し、努力を支援する必要がある。また、現時点での一般財政支援は時期尚早と考えられるが、今後財政支援への潮流が強まることは必至であり、状況を注視する必要がある。
(3)セネガルでは、西アフリカ地域に於ける拠点という位置づけから、比較的先駆的な試みや多様な協力モダリ ティーによる協力を展開してきた。こうした過去の技術協力の実績を踏まえ、セネガルに蓄積された知見・経験を「域内協力」に発展させていく視点を持つこと が重要である。
(4)今般の食糧問題に対処するため、ワッド大統領は大胆な農業政策を実施し、食糧の輸入依存からの脱却を図っている。この自助努力に対し我が国も支援を検討する必要がある。
(5)教育は国の礎との哲学のもと、ワッド大統領は国家予算の4割を教育に当てている。教育分野に関しては我が国も以前から重点的に支援を行ってきているが、引き続き協力する必要がある。






