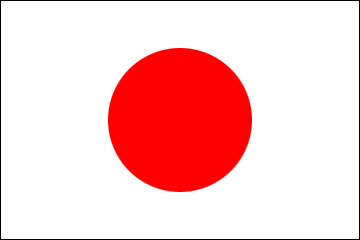メールマガジン2023年4月号
令和5年4月7日
【在セネガル日本大使館メールマガジン 2023/4/7 第11号】
◆ 目次 ◆
1 「伊澤修駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「寄稿文」
4 「領事便り」
5 「政治・経済」
6 「広報・文化便り」
***********************
1 伊澤修駐セネガル日本大使挨拶
3月は気温が低めの日が続きましたが、ここ数日気温が上がってきて日中は少し蒸し暑く感じるようになりました。皆様如何お過ごしでしょうか。
3月9日に天皇誕生日レセプションを開催しました。今年は招待客をコロナ前の規模に戻して、300名以上の方に参加して頂くことができました。本使としては、このレセプションを通じて日本とセネガルの友好関係を促進すること、特にこの機会にセネガルの各分野の方々に日本とのつながりを感じて頂くことが重要だと考えて、当地で活躍される邦人企業の皆様に企業展示をお願いしました。企業展示も含めてレセプションは上手く行き、参加された多くの皆様から高い評価を頂きました。
料理の中では焼き鳥と寿司に長蛇の列ができるほどの人気がありました。やはりセネガルでは日本料理といえば寿司と焼き鳥がダントツ人気だと実感しました。本使は、日本のカレーライスがセネガル料理に通じるところがあると考えてカレーライスの宣伝をしているのですが、日本の白米に不慣れなセネガル人にはまだまだの感じがします。工夫として、日本の白米の代わりに地元セネガルの米を使うことを考えています。
レセプションでの催しとして、ティエスでレスリングの指導をしている魚住さんにセネガル人と一緒にセネガル相撲の実演をして頂きました。実戦なのでお二人の気迫が伝わってきてとても迫力がありました。魚住様ありがとうございました。
先日4日にはセネガルの独立記念日のパレードを見ました。今年はコロナ以前に戻して国民広場で行われ、規模もかなり大きく、盛大なイベントとなりました。
日本では自衛隊により行われる自衛隊記念日のパレードがありますが、セネガルの場合、パレードには軍だけではなく地域の代表や学校の代表等の民間の団体や警察や消防といった他の行政機関からも参加があり、かなり多くの階層から参加者が集められています。地域代表や学校グループにはたくさんの子供達も参加していて、彼らが堂々と行進をしているのを見て、微笑ましく思うとともに、彼らの誇りも感じられて、将来のセネガルを担う若者達に頑張って欲しいという気持ちになりました。セネガル軍の砲兵隊、装甲車や機銃部隊等も多数行進し、不安定な情勢が続く西アフリカにおいて、なんとしてもセネガルの安全を確保していくという政権の強い意志を感じました。
話は前後しますが、3月14日に当地で活動する主な日本企業の方々を公邸にお招きして日本企業連絡会を立ち上げました。これまで邦人企業の方々と多く意見交換や視察を行ってきましたが、セネガルでビジネスを進めている皆様が直面する問題には共通するところもあることから、情報交換と同時にセネガル政府への対応ぶりについて調整を図るべく初めて開催しました。たくさんの貴重な意見を頂きましたので、大使館業務の参考にさせて頂くとともにこの連絡会を定期化していこうと考えています。
2 大使館からのお知らせ
○2023年4月、5月の休館日のお知らせ
4月 4日(火) 独立記念日
4月10日(月) イースター翌月曜日
5月 1日(月) メーデー
5月18日(木) キリスト昇天祭
5月29日(月) 聖霊降臨祭翌月曜日
○ラマダーンの日程
今年のラマダーンは、3月23日から4月22日までが予定されています。(終了日は多少前後する可能性があります。)
○ダカール補習授業校の卒業式(3月25日)と入学式(4月1日)が開催されました。
(卒業式の様子) https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01125.html
(入学式の様子) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uKkVWqENXVSkWGcwiys38Ty4zRpiUNGxXMgFqRMPAaSmdBsGWXcNTRDdDxsX3h24l&id=100078921276471
3 寄稿 ーパパ・ゲイ日・セネガル友好協会会長
私と日本との出会い
(1)はじめに
1982年の終わりに、ある日Le Soleilという公共日刊紙で在セネガル日本大使館の留学生募集の広告を見て、申請書を提出し、テストに合格して、1983年に日本に留学することになりました。予定は、まず大阪外国語大学で半年ほど日本語を学んでから、東京の明治大学で1年半、経済学の修士課程で研究を行うことでありました。当時は、明治大学とダカ-ル大学の交流プログラムあったため、明治大学に送られました。
1983年10月12日セネガルを出発し、日本に到着しました。当時ヨーロッパから日本への直行便はなく、ダカ-ルからルフトハンザ航空に乗って、デュッセルドルフ、ブリュッセル、アンカレッジを経由して、約48時間の長旅を経て大阪に着きました。そこで、日本人の若い学生のグループが大阪国際空港に迎えに来て、大阪外国語大学の留学生寮に連れて行ってくれました。日本と日本人との最初の具体的な出会いの始まりでもありました。当時、私は30歳でしたが日本語を全く話せませんでした。すでに結婚しており、生後数か月の娘がおり、後に東京にいる私と合流する予定でした。
仕事でヨーロッパに1週間ほど滞在する機会はありましたが、アフリカ大陸の外に出る初めての長期滞在でした。実は、私はダカール大学で経済学の修士号(経営管理専攻)を取得し、セネガル国立行政大学院で経済財務専門の卒業証書を取得した後、1979年から、経済財務省で債務投資部門のアフリカ・ アジア・ 東方諸国課課長を務めていました。
(2)日本との出会い
大阪での新生活は、日本での生活に溶け込むにはとてもよいものでした。寮は箕面市の山腹にあり、周囲の自然と風景の素晴らしい景色を眺めることができました。勉強しやすい環境でした。町からかなり離れていていましたが、交通が便利で、バスに乗って箕面市を訪問したり、最寄りの駅から電車で梅田まで行くことがありました。
ただ、最初は食生活に困りました。食堂の食べ物が甘く、私たちが慣れている辛い食べ物とは大きく異なっていたので、まず日本料理を発見し、その味に慣れなければなりませんでした。そこで、毎週2、3回、箕面市、梅田などを訪ねて、食べられる西洋料理を探しました。
大阪での第一の目的は、言語を学び、日本社会を理解することでした。寮には、様々なアフリカ、アジア、ヨーロッパおよびアメリカから来た約50人の留学生が集まっていました。そこでは言葉だけでなく、日本の文化や歴史も学べ、学生間の交流、他者への広い開放性、社会統合を促進する豊かな環境がありました。
(3)言語学習
言語学習は集中的に約6か月間続きました。日本社会の文化と歴史に加えて、言語教育全般:読み書き(ひらがな、カタカナ、漢字)、活用、文法、構文、口頭表現に重点が置かれていました。このコースは、言語の一般的な知識に加えて、日本での大学院研究での言語活用能力を高める基礎となりました。
広島や奈良などへの研修旅行もありました。マツダ、日立、日本鋼管などの有名企業を訪問することにより、日本のさまざまな文化、歴史、経済的側面を発見することができました。
(4)日本での生活
私の日本での生活は、大阪外大留学生キャンパスに到着したところから始まりました。そこでは、あらゆる国籍の学生が存在し、そのほとんどは大学院生でした。日常生活で、大阪の街に出かけた時に偶然の出会いが続きました。特に、若い日本人 (生徒や高校生) との偶然の交流がありました。私は好奇心旺盛だったが、外国語でちょっとした会話を始めることに慣れるのが大変でした。
(5)東京での生活
1984年3月末、大阪での語学研修が終了した後、東京に引っ越して、渋谷の近くにある駒場留学生会館に滞在し始めました。東京での生活は、駒場寮と明治大学の間を地下鉄で移動することでさらに活発になりました。人口の多さが印象的でした。
修士課程は、教授による講義とアシスタントによるゼミに分かれていました。外国人留学生(スーダン1人、中国人2人)もいました 。週に1回の語学レッスンと専任のチューターによる専門支援も受けていました。これらの語学学習に加えて、論文指導の先生の下で経済統合に関する経済学の修士論文を書くことを目指して研究を続けました。研究書が充実していた大学図書館で主に活動していましたが、アジア研究所の図書館、または JETRO や他の大学や研究機関等でも研究を行いました。
学生としての生活とは別に、駒場会館では外国人留学生との交流ができ、レストランのメニューも豊富で、静かに勉強することができました。また、大都市東京を徐々に見ることができ、大学外で人々と出会い、新しい視野を獲得することができました。特に、日本大使館参事官が推薦した住友銀行の幹部とJICAの幹部の2人に連絡を取ることができたことも様々な面で役立ちました。この二方の会合に招待され、日本のプロの世界を初めて具体的に見ることができました。このように、いくつかの専門家サークルの高位の人々に会うことができ、実り多い交流があり、研究や日本に対する見方が広がりました。その後の2年間は、遠足や研修旅行、企業訪問、研究機関でのセミナーなどを通じて、多く課題の発見をすることができました。
その間、駒場会館から東京の中心部、銀座近くの月島にある公団住宅に引っ越し、1985 年5月に家族が来日しました。 そこでは、人生もこれらの発展と時間の経過とともに変化しました。
研究は順調で、1984年から1985年の間にすでに3件の紀要論文を提出することができ、修士論文を書きながら研究を続けていました。1986年3月に、開発経済学の修士号(国際経済開発統合)を取得しました。その後、博士課程に入学し、奨学金が延長されることになりました。
新たな出会いが新たな機会を生み、翻訳会社で翻訳のアルバイトができるようになり、また、当時セネガルでプロジェクトに取り組んでいたコンサルタントや企業とパートタイムで働くこともできました.
妻はアフリカのガボンとルワンダの在日大使館に就職し、娘は家から近い築地の幼稚園に通っていました。そのため、アルバイトで隙間を埋めながら、静かに勉強を続けることができました。在日セネガル人や外国人、日本人との出会い、様々な文化行事(祭り、花見など)への参加、史跡巡りなど楽しいひとときでした。
1987年に、大学の近くにある静かな小石川に引っ越しました。1989年、論文をまだ提出していないうちに奨学金の期限が切れてしまいました。実際に、当時、博士課程の修業期間に明確な定めはありませんでした。知り合いのおかげで、広尾の日本青年海外協力隊研修センターですぐに仕事を見つけることができました。そこで数か月英語を教えて、その後、西新宿にあった情報化を専門とするワークブレインコンサルティング会社で正社員の仕事を見つけました。それから、システム・アナリストとしての新しい職業に就きながら、論文指導教授とそのアシスタントと協力して博士論文の執筆を続けました。
システム開発部が、スーパーマーケット向けのマーケティングシステムを含むいくつかのプロジェクトに取り組んでいましたが、英国の工場を買収した大手電動鋸製造会社のために MAPICS と呼ばれる IBM の生産管理ソフトウェアをカスタマイズしたことは、私に最も印象をつけられたプロジェクトの 1 つです。
部長の指揮の下、生産管理システムの経験がある彼の 2 人の部長アシスタント、2 人の女性アシスタント、およびシステム・エンジニアと一緒にチームで働きました。チーム内での調整は継続的でした。作業について定期的に話し合い、タスクの進捗状況は常に監視されていました。
実務研修も業務の枠内で継続的に行われ、さらに生産管理システムの設計・開発の研修会にも度々派遣されました。 MAPICS の専門家 (外部コンサルタント) から、定期的に MAPICS システムのトレーニングを受けました。 このように、MAPICSシステムは約 10 か月後にカスタマイズされ、英国の子会社に正常に納入されました。作業は必ずしも簡単なものではありませんでした。締め切りと品質条件を満たすには、多くの努力、忍耐と厳格さ、フォローアップが必要でした。時には眠れない夜もありましたが、充実していました。
そのほか、韓国人1人、アメリカ人1人、フランス人1人、そして多くの留学生が海外での経験を積んでいたため、会社がかなり国際化されていました。そして雰囲気が良く、交流が盛んでありました。
1992 年 3 月に論文を提出し、博士号が授与されました。そこでも、これまでの努力と直面した困難を考えると、大きな満足感が得られました。その後、日本に残り、仕事を続けようとしましたが、1992 年に父が亡くなり、その翌年母が病気になり、セネガルに戻ることにしました。
(6)セネガル 帰国後の活動
1993 年 10 月にセネガルに戻り、最初はコンサル事務所を作ることを計画しながら、ダカールのカナダ国際開発センターで、西アフリカの経済統合に関する英仏語の本を出版するための編集者補助として働き始めました。その後、1994 年 7 月から 2005 年 3 月まで、JICA に内部コンサルタントの形で、駐在員代表のミッション・マネージャー、そしてアドバイザーを務めました。
その間、1997 年には、日本とセネガルの関係と交流を促進するために、調査、コンサルティング、通訳と翻訳、仲介、広報などを提供する会社を設立ました。また、JICA へのコンサルティング活動を継続しながら、セネガルで活動する日本の組織のニーズに応え、セネガルと日本の架け橋となるようにこれらの活動を拡張しました。これまでに多くの成果を上げてきましたが、新しい視点が生まれつつあるこの時期に、この方向性を貫いていきたいと考えています。
現在のセネガルの進化により、新たな可能性が開けつつありますが、日本とセネガルを結ぶ架け橋として、交流の発展に貢献できることを願っております。
(7)終わりに
1995年にはASENIというセネガルと日本の友好を促進するための協会を設立し、会長に就任しました。日本に 10 年間住み、日本との専門的な協力を 30 年間行ってきた今でも、目標は、これまでに蓄積してきたすべての経験と成果を活用して、両国間の友好的で実りある関係を強化することです。日本に関心のあるすべての人々や日本で訓練を受けたすべての人に、両国間の友好的で相互に実りある関係を強化できるよう努めていくのが私たちの使命です。
4 領事便り
○先日、サーフィンに行こうとビーチ近くのアスファルト道路を裸足で歩いていたら、足の裏を火傷し大きな水ぶくれをこさえてしまいました。これから暑さが厳しくなると砂浜も焼けるような熱さになりますので、海岸ではサンダルを履くなどして怪我のないようご注意を!
<旅券のオンライン申請開始>
○3月27日より旅券のオンライン申請が開始されました。
○日本国外から旅券のオンライン申請をする場合は、在留届(ORRネット)アカウントを利用して旅券申請を行い、新しい旅券完成後に在セネガル大使館に受け取りに来ていただくことになります。詳しくは下記URLをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
○在セネガル大使館で受け取る場合はクレジットカード支払いができません。領事窓口での受け取り時に現金にてお支払いください。
○引き続き領事窓口での旅券申請も受け付けております。
○旅券の増補は廃止されました。
<領事手数料の改定(令和5年度)>
○4月1日から領事手数料が改訂されました。詳細は当館HPをご覧ください。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00901.html
○3月31日以前に各種申請を行った場合、交付日が4月1日以降であっても、手数料は改定前のものとなります。
5 政治・経済
○セネガル国内における野党デモ等の動き
2024年2月に予定されている大統領選挙を控え、セネガル国内各地では、政治的緊張が高まりつつあります。
3月16日には、野党PASTEFのソンコ党首の裁判(観光大臣への名誉毀損容疑)に関連して、ダカール市内・郊外の各地で野党支持者と治安当局との衝突が発生し、死者3名が発生、一部の仏系商業施設や公共バス等が放火される等の被害も生じました。その後、同裁判は3月30日に延期され、同日にはソンコ党首が裁判所出頭を拒む中、名誉毀損罪の有罪判決(執行猶予付き懲役2か月及び損害賠償2億FCFAの支払)が下されました。裁判判決後には野党支持者と当局との衝突は沈静化し、4月3日に予定されていたデモも延期となりましたが、検察側が控訴の意向を表明しており、今後の裁判の動向によっては再び抗議デモ等が行われる可能性があります。
今後、大統領選挙までの期間には、こうした与野党の対立や野党関係者の裁判や逮捕等に関連するデモや衝突が散発的に生ずる可能性があります。
在留邦人の皆さまにおかれては、領事メール等による安全情報の提供に十分ご留意ください。まだ在留届やたびレジを登録されていない方がいらっしゃる場合には、迅速な情報提供及び緊急事態発生時の安否確認のため、速やかにオンライン登録をお願いいたします。
また、デモや集会が行われている場合には絶対に近づかず、やむを得ず近辺を走行する場合には車両の窓を閉める等、十分な安全確保をお願いいたします。
○3月17日、伊澤大使は、大使館にて行われた令和4年度対セネガル草の根・人間の安全保障無償資金協力「ムボロビラン村農業用ソーラーポンプシステム整備計画」の署名式に参加しました。
(式典の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01105.html
○3月20日、カーボベルデのプライア市内で、日本政府の支援でWFP西アフリカ地域事務所が実施する学校給食プログラムの食料の引渡式が行われました。
(式典の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01121.html
○当館が所掌する4か国(セネガル、カーボベルデ、ガンビア、ギニアビサウ)の政治経済関連の一般情報は、毎月上旬に当館のHP「セネガル基礎情報」及び「新着情報」に「在セネガル大使館月例報告」として掲載しております。ご関心のある方は以下のリンクをご参照ください。
(参考)月例報告:https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01078.html
6 広報・文化便り
○天皇誕生日レセプション
3月9日、日本国大使公邸にて天皇誕生日レセプションが開催されました。
(当日の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01099.html
○3月9日、日本大使公邸にて、伊澤大使は、セネガルのアワ・マリー・コル・セック国務大臣(採取産業透明性イニシアティブ(EITI)セネガル国家委員長、野口英世アフリカ賞選考委員、元保健・社会活動大臣)への令和4年度外務大臣表彰の伝達式を行いました。式典では、同国務大臣の知人である林玲子国立社会保障・人口問題研究所副所長からの祝辞及び謝辞のメッセージも読み上げられました。
(式典の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01098.html
○3月2、3日、当館は現地メディア向けプレスツアーを実施し、カゴメ株式会社のトマト農園(サン・ルイ州ンビロール村)と技術協力プロジェクト「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ3)(サン・ルイ州デビ・チゲ地区)のサイトを訪問しました。
(当日の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01102.html
○3月18日、当館は元国費留学生懇親会を開催し、今後のセネガル人学生による日本留学の振興について意見交換しました。
(当日の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01109.html
○3月21日、伊澤駐セネガル日本大使公邸において、第35回俳句コンクールの授賞式が開催されました。
(授賞式の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01123.html
○当館では、日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本関連行事のほか、知り合いの方のご活動等についての情報を( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )までお知らせください。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。当館HPやSNSへの掲載は随時行います。
○当館のSNSアカウントは以下のとおりです。日・セネガル関係強化のため、是非ご関心のある投稿のRTやシェア等、皆さまのご協力をお願いいたします。
TW:https://twitter.com/JapanEmbSenegal
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471
----------------------------------------------------------------------
[在セネガル日本大使館メールマガジン]
○本メールマガジンに関するご意見・ご要望は以下のメールアドレスあてに送信してください。新規配信登録のご希望もこちらまでお寄せください。
( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )
○参考ホームページ
首相官邸ホームページ ( www.kantei.go.jp )
外務省ホームページ ( www.mofa.go.jp/mofaj/ )
当館ホームページ (https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
当館Twitter ( https://twitter.com/JapanEmbSenegal )
当館Facebook( https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471 )
○発行:在セネガル日本大使館
Ambassade du Japon au Senegal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Senegal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55
◆ 目次 ◆
1 「伊澤修駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「寄稿文」
4 「領事便り」
5 「政治・経済」
6 「広報・文化便り」
***********************
1 伊澤修駐セネガル日本大使挨拶
3月は気温が低めの日が続きましたが、ここ数日気温が上がってきて日中は少し蒸し暑く感じるようになりました。皆様如何お過ごしでしょうか。
3月9日に天皇誕生日レセプションを開催しました。今年は招待客をコロナ前の規模に戻して、300名以上の方に参加して頂くことができました。本使としては、このレセプションを通じて日本とセネガルの友好関係を促進すること、特にこの機会にセネガルの各分野の方々に日本とのつながりを感じて頂くことが重要だと考えて、当地で活躍される邦人企業の皆様に企業展示をお願いしました。企業展示も含めてレセプションは上手く行き、参加された多くの皆様から高い評価を頂きました。
料理の中では焼き鳥と寿司に長蛇の列ができるほどの人気がありました。やはりセネガルでは日本料理といえば寿司と焼き鳥がダントツ人気だと実感しました。本使は、日本のカレーライスがセネガル料理に通じるところがあると考えてカレーライスの宣伝をしているのですが、日本の白米に不慣れなセネガル人にはまだまだの感じがします。工夫として、日本の白米の代わりに地元セネガルの米を使うことを考えています。
レセプションでの催しとして、ティエスでレスリングの指導をしている魚住さんにセネガル人と一緒にセネガル相撲の実演をして頂きました。実戦なのでお二人の気迫が伝わってきてとても迫力がありました。魚住様ありがとうございました。
先日4日にはセネガルの独立記念日のパレードを見ました。今年はコロナ以前に戻して国民広場で行われ、規模もかなり大きく、盛大なイベントとなりました。
日本では自衛隊により行われる自衛隊記念日のパレードがありますが、セネガルの場合、パレードには軍だけではなく地域の代表や学校の代表等の民間の団体や警察や消防といった他の行政機関からも参加があり、かなり多くの階層から参加者が集められています。地域代表や学校グループにはたくさんの子供達も参加していて、彼らが堂々と行進をしているのを見て、微笑ましく思うとともに、彼らの誇りも感じられて、将来のセネガルを担う若者達に頑張って欲しいという気持ちになりました。セネガル軍の砲兵隊、装甲車や機銃部隊等も多数行進し、不安定な情勢が続く西アフリカにおいて、なんとしてもセネガルの安全を確保していくという政権の強い意志を感じました。
話は前後しますが、3月14日に当地で活動する主な日本企業の方々を公邸にお招きして日本企業連絡会を立ち上げました。これまで邦人企業の方々と多く意見交換や視察を行ってきましたが、セネガルでビジネスを進めている皆様が直面する問題には共通するところもあることから、情報交換と同時にセネガル政府への対応ぶりについて調整を図るべく初めて開催しました。たくさんの貴重な意見を頂きましたので、大使館業務の参考にさせて頂くとともにこの連絡会を定期化していこうと考えています。
2 大使館からのお知らせ
○2023年4月、5月の休館日のお知らせ
4月 4日(火) 独立記念日
4月10日(月) イースター翌月曜日
5月 1日(月) メーデー
5月18日(木) キリスト昇天祭
5月29日(月) 聖霊降臨祭翌月曜日
○ラマダーンの日程
今年のラマダーンは、3月23日から4月22日までが予定されています。(終了日は多少前後する可能性があります。)
○ダカール補習授業校の卒業式(3月25日)と入学式(4月1日)が開催されました。
(卒業式の様子) https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01125.html
(入学式の様子) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uKkVWqENXVSkWGcwiys38Ty4zRpiUNGxXMgFqRMPAaSmdBsGWXcNTRDdDxsX3h24l&id=100078921276471
3 寄稿 ーパパ・ゲイ日・セネガル友好協会会長
私と日本との出会い
(1)はじめに
1982年の終わりに、ある日Le Soleilという公共日刊紙で在セネガル日本大使館の留学生募集の広告を見て、申請書を提出し、テストに合格して、1983年に日本に留学することになりました。予定は、まず大阪外国語大学で半年ほど日本語を学んでから、東京の明治大学で1年半、経済学の修士課程で研究を行うことでありました。当時は、明治大学とダカ-ル大学の交流プログラムあったため、明治大学に送られました。
1983年10月12日セネガルを出発し、日本に到着しました。当時ヨーロッパから日本への直行便はなく、ダカ-ルからルフトハンザ航空に乗って、デュッセルドルフ、ブリュッセル、アンカレッジを経由して、約48時間の長旅を経て大阪に着きました。そこで、日本人の若い学生のグループが大阪国際空港に迎えに来て、大阪外国語大学の留学生寮に連れて行ってくれました。日本と日本人との最初の具体的な出会いの始まりでもありました。当時、私は30歳でしたが日本語を全く話せませんでした。すでに結婚しており、生後数か月の娘がおり、後に東京にいる私と合流する予定でした。
仕事でヨーロッパに1週間ほど滞在する機会はありましたが、アフリカ大陸の外に出る初めての長期滞在でした。実は、私はダカール大学で経済学の修士号(経営管理専攻)を取得し、セネガル国立行政大学院で経済財務専門の卒業証書を取得した後、1979年から、経済財務省で債務投資部門のアフリカ・ アジア・ 東方諸国課課長を務めていました。
(2)日本との出会い
大阪での新生活は、日本での生活に溶け込むにはとてもよいものでした。寮は箕面市の山腹にあり、周囲の自然と風景の素晴らしい景色を眺めることができました。勉強しやすい環境でした。町からかなり離れていていましたが、交通が便利で、バスに乗って箕面市を訪問したり、最寄りの駅から電車で梅田まで行くことがありました。
ただ、最初は食生活に困りました。食堂の食べ物が甘く、私たちが慣れている辛い食べ物とは大きく異なっていたので、まず日本料理を発見し、その味に慣れなければなりませんでした。そこで、毎週2、3回、箕面市、梅田などを訪ねて、食べられる西洋料理を探しました。
大阪での第一の目的は、言語を学び、日本社会を理解することでした。寮には、様々なアフリカ、アジア、ヨーロッパおよびアメリカから来た約50人の留学生が集まっていました。そこでは言葉だけでなく、日本の文化や歴史も学べ、学生間の交流、他者への広い開放性、社会統合を促進する豊かな環境がありました。
(3)言語学習
言語学習は集中的に約6か月間続きました。日本社会の文化と歴史に加えて、言語教育全般:読み書き(ひらがな、カタカナ、漢字)、活用、文法、構文、口頭表現に重点が置かれていました。このコースは、言語の一般的な知識に加えて、日本での大学院研究での言語活用能力を高める基礎となりました。
広島や奈良などへの研修旅行もありました。マツダ、日立、日本鋼管などの有名企業を訪問することにより、日本のさまざまな文化、歴史、経済的側面を発見することができました。
(4)日本での生活
私の日本での生活は、大阪外大留学生キャンパスに到着したところから始まりました。そこでは、あらゆる国籍の学生が存在し、そのほとんどは大学院生でした。日常生活で、大阪の街に出かけた時に偶然の出会いが続きました。特に、若い日本人 (生徒や高校生) との偶然の交流がありました。私は好奇心旺盛だったが、外国語でちょっとした会話を始めることに慣れるのが大変でした。
(5)東京での生活
1984年3月末、大阪での語学研修が終了した後、東京に引っ越して、渋谷の近くにある駒場留学生会館に滞在し始めました。東京での生活は、駒場寮と明治大学の間を地下鉄で移動することでさらに活発になりました。人口の多さが印象的でした。
修士課程は、教授による講義とアシスタントによるゼミに分かれていました。外国人留学生(スーダン1人、中国人2人)もいました 。週に1回の語学レッスンと専任のチューターによる専門支援も受けていました。これらの語学学習に加えて、論文指導の先生の下で経済統合に関する経済学の修士論文を書くことを目指して研究を続けました。研究書が充実していた大学図書館で主に活動していましたが、アジア研究所の図書館、または JETRO や他の大学や研究機関等でも研究を行いました。
学生としての生活とは別に、駒場会館では外国人留学生との交流ができ、レストランのメニューも豊富で、静かに勉強することができました。また、大都市東京を徐々に見ることができ、大学外で人々と出会い、新しい視野を獲得することができました。特に、日本大使館参事官が推薦した住友銀行の幹部とJICAの幹部の2人に連絡を取ることができたことも様々な面で役立ちました。この二方の会合に招待され、日本のプロの世界を初めて具体的に見ることができました。このように、いくつかの専門家サークルの高位の人々に会うことができ、実り多い交流があり、研究や日本に対する見方が広がりました。その後の2年間は、遠足や研修旅行、企業訪問、研究機関でのセミナーなどを通じて、多く課題の発見をすることができました。
その間、駒場会館から東京の中心部、銀座近くの月島にある公団住宅に引っ越し、1985 年5月に家族が来日しました。 そこでは、人生もこれらの発展と時間の経過とともに変化しました。
研究は順調で、1984年から1985年の間にすでに3件の紀要論文を提出することができ、修士論文を書きながら研究を続けていました。1986年3月に、開発経済学の修士号(国際経済開発統合)を取得しました。その後、博士課程に入学し、奨学金が延長されることになりました。
新たな出会いが新たな機会を生み、翻訳会社で翻訳のアルバイトができるようになり、また、当時セネガルでプロジェクトに取り組んでいたコンサルタントや企業とパートタイムで働くこともできました.
妻はアフリカのガボンとルワンダの在日大使館に就職し、娘は家から近い築地の幼稚園に通っていました。そのため、アルバイトで隙間を埋めながら、静かに勉強を続けることができました。在日セネガル人や外国人、日本人との出会い、様々な文化行事(祭り、花見など)への参加、史跡巡りなど楽しいひとときでした。
1987年に、大学の近くにある静かな小石川に引っ越しました。1989年、論文をまだ提出していないうちに奨学金の期限が切れてしまいました。実際に、当時、博士課程の修業期間に明確な定めはありませんでした。知り合いのおかげで、広尾の日本青年海外協力隊研修センターですぐに仕事を見つけることができました。そこで数か月英語を教えて、その後、西新宿にあった情報化を専門とするワークブレインコンサルティング会社で正社員の仕事を見つけました。それから、システム・アナリストとしての新しい職業に就きながら、論文指導教授とそのアシスタントと協力して博士論文の執筆を続けました。
システム開発部が、スーパーマーケット向けのマーケティングシステムを含むいくつかのプロジェクトに取り組んでいましたが、英国の工場を買収した大手電動鋸製造会社のために MAPICS と呼ばれる IBM の生産管理ソフトウェアをカスタマイズしたことは、私に最も印象をつけられたプロジェクトの 1 つです。
部長の指揮の下、生産管理システムの経験がある彼の 2 人の部長アシスタント、2 人の女性アシスタント、およびシステム・エンジニアと一緒にチームで働きました。チーム内での調整は継続的でした。作業について定期的に話し合い、タスクの進捗状況は常に監視されていました。
実務研修も業務の枠内で継続的に行われ、さらに生産管理システムの設計・開発の研修会にも度々派遣されました。 MAPICS の専門家 (外部コンサルタント) から、定期的に MAPICS システムのトレーニングを受けました。 このように、MAPICSシステムは約 10 か月後にカスタマイズされ、英国の子会社に正常に納入されました。作業は必ずしも簡単なものではありませんでした。締め切りと品質条件を満たすには、多くの努力、忍耐と厳格さ、フォローアップが必要でした。時には眠れない夜もありましたが、充実していました。
そのほか、韓国人1人、アメリカ人1人、フランス人1人、そして多くの留学生が海外での経験を積んでいたため、会社がかなり国際化されていました。そして雰囲気が良く、交流が盛んでありました。
1992 年 3 月に論文を提出し、博士号が授与されました。そこでも、これまでの努力と直面した困難を考えると、大きな満足感が得られました。その後、日本に残り、仕事を続けようとしましたが、1992 年に父が亡くなり、その翌年母が病気になり、セネガルに戻ることにしました。
(6)セネガル 帰国後の活動
1993 年 10 月にセネガルに戻り、最初はコンサル事務所を作ることを計画しながら、ダカールのカナダ国際開発センターで、西アフリカの経済統合に関する英仏語の本を出版するための編集者補助として働き始めました。その後、1994 年 7 月から 2005 年 3 月まで、JICA に内部コンサルタントの形で、駐在員代表のミッション・マネージャー、そしてアドバイザーを務めました。
その間、1997 年には、日本とセネガルの関係と交流を促進するために、調査、コンサルティング、通訳と翻訳、仲介、広報などを提供する会社を設立ました。また、JICA へのコンサルティング活動を継続しながら、セネガルで活動する日本の組織のニーズに応え、セネガルと日本の架け橋となるようにこれらの活動を拡張しました。これまでに多くの成果を上げてきましたが、新しい視点が生まれつつあるこの時期に、この方向性を貫いていきたいと考えています。
現在のセネガルの進化により、新たな可能性が開けつつありますが、日本とセネガルを結ぶ架け橋として、交流の発展に貢献できることを願っております。
(7)終わりに
1995年にはASENIというセネガルと日本の友好を促進するための協会を設立し、会長に就任しました。日本に 10 年間住み、日本との専門的な協力を 30 年間行ってきた今でも、目標は、これまでに蓄積してきたすべての経験と成果を活用して、両国間の友好的で実りある関係を強化することです。日本に関心のあるすべての人々や日本で訓練を受けたすべての人に、両国間の友好的で相互に実りある関係を強化できるよう努めていくのが私たちの使命です。
4 領事便り
○先日、サーフィンに行こうとビーチ近くのアスファルト道路を裸足で歩いていたら、足の裏を火傷し大きな水ぶくれをこさえてしまいました。これから暑さが厳しくなると砂浜も焼けるような熱さになりますので、海岸ではサンダルを履くなどして怪我のないようご注意を!
<旅券のオンライン申請開始>
○3月27日より旅券のオンライン申請が開始されました。
○日本国外から旅券のオンライン申請をする場合は、在留届(ORRネット)アカウントを利用して旅券申請を行い、新しい旅券完成後に在セネガル大使館に受け取りに来ていただくことになります。詳しくは下記URLをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
○在セネガル大使館で受け取る場合はクレジットカード支払いができません。領事窓口での受け取り時に現金にてお支払いください。
○引き続き領事窓口での旅券申請も受け付けております。
○旅券の増補は廃止されました。
<領事手数料の改定(令和5年度)>
○4月1日から領事手数料が改訂されました。詳細は当館HPをご覧ください。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00901.html
○3月31日以前に各種申請を行った場合、交付日が4月1日以降であっても、手数料は改定前のものとなります。
5 政治・経済
○セネガル国内における野党デモ等の動き
2024年2月に予定されている大統領選挙を控え、セネガル国内各地では、政治的緊張が高まりつつあります。
3月16日には、野党PASTEFのソンコ党首の裁判(観光大臣への名誉毀損容疑)に関連して、ダカール市内・郊外の各地で野党支持者と治安当局との衝突が発生し、死者3名が発生、一部の仏系商業施設や公共バス等が放火される等の被害も生じました。その後、同裁判は3月30日に延期され、同日にはソンコ党首が裁判所出頭を拒む中、名誉毀損罪の有罪判決(執行猶予付き懲役2か月及び損害賠償2億FCFAの支払)が下されました。裁判判決後には野党支持者と当局との衝突は沈静化し、4月3日に予定されていたデモも延期となりましたが、検察側が控訴の意向を表明しており、今後の裁判の動向によっては再び抗議デモ等が行われる可能性があります。
今後、大統領選挙までの期間には、こうした与野党の対立や野党関係者の裁判や逮捕等に関連するデモや衝突が散発的に生ずる可能性があります。
在留邦人の皆さまにおかれては、領事メール等による安全情報の提供に十分ご留意ください。まだ在留届やたびレジを登録されていない方がいらっしゃる場合には、迅速な情報提供及び緊急事態発生時の安否確認のため、速やかにオンライン登録をお願いいたします。
また、デモや集会が行われている場合には絶対に近づかず、やむを得ず近辺を走行する場合には車両の窓を閉める等、十分な安全確保をお願いいたします。
○3月17日、伊澤大使は、大使館にて行われた令和4年度対セネガル草の根・人間の安全保障無償資金協力「ムボロビラン村農業用ソーラーポンプシステム整備計画」の署名式に参加しました。
(式典の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01105.html
○3月20日、カーボベルデのプライア市内で、日本政府の支援でWFP西アフリカ地域事務所が実施する学校給食プログラムの食料の引渡式が行われました。
(式典の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01121.html
○当館が所掌する4か国(セネガル、カーボベルデ、ガンビア、ギニアビサウ)の政治経済関連の一般情報は、毎月上旬に当館のHP「セネガル基礎情報」及び「新着情報」に「在セネガル大使館月例報告」として掲載しております。ご関心のある方は以下のリンクをご参照ください。
(参考)月例報告:https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01078.html
6 広報・文化便り
○天皇誕生日レセプション
3月9日、日本国大使公邸にて天皇誕生日レセプションが開催されました。
(当日の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01099.html
○3月9日、日本大使公邸にて、伊澤大使は、セネガルのアワ・マリー・コル・セック国務大臣(採取産業透明性イニシアティブ(EITI)セネガル国家委員長、野口英世アフリカ賞選考委員、元保健・社会活動大臣)への令和4年度外務大臣表彰の伝達式を行いました。式典では、同国務大臣の知人である林玲子国立社会保障・人口問題研究所副所長からの祝辞及び謝辞のメッセージも読み上げられました。
(式典の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01098.html
○3月2、3日、当館は現地メディア向けプレスツアーを実施し、カゴメ株式会社のトマト農園(サン・ルイ州ンビロール村)と技術協力プロジェクト「セネガル川流域灌漑稲作生産性向上プロジェクト(PAPRIZ3)(サン・ルイ州デビ・チゲ地区)のサイトを訪問しました。
(当日の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01102.html
○3月18日、当館は元国費留学生懇親会を開催し、今後のセネガル人学生による日本留学の振興について意見交換しました。
(当日の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01109.html
○3月21日、伊澤駐セネガル日本大使公邸において、第35回俳句コンクールの授賞式が開催されました。
(授賞式の様子)https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01123.html
○当館では、日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本関連行事のほか、知り合いの方のご活動等についての情報を( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )までお知らせください。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。当館HPやSNSへの掲載は随時行います。
○当館のSNSアカウントは以下のとおりです。日・セネガル関係強化のため、是非ご関心のある投稿のRTやシェア等、皆さまのご協力をお願いいたします。
TW:https://twitter.com/JapanEmbSenegal
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471
----------------------------------------------------------------------
[在セネガル日本大使館メールマガジン]
○本メールマガジンに関するご意見・ご要望は以下のメールアドレスあてに送信してください。新規配信登録のご希望もこちらまでお寄せください。
( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )
○参考ホームページ
首相官邸ホームページ ( www.kantei.go.jp )
外務省ホームページ ( www.mofa.go.jp/mofaj/ )
当館ホームページ (https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
当館Twitter ( https://twitter.com/JapanEmbSenegal )
当館Facebook( https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471 )
○発行:在セネガル日本大使館
Ambassade du Japon au Senegal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Senegal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55