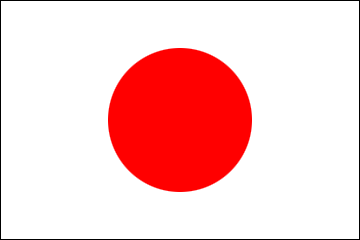メールマガジン2024年11月号
令和6年11月5日
【在セネガル日本大使館メールマガジン 2024/11/5 第30号】
◆ 目次 ◆
1 「伊澤修駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「寄稿文」
4 「領事便り」
5 「政治・経済」
6 「広報・文化便り」
***********************
1 伊澤修駐セネガル日本大使挨拶
10月後半からは乾期に入りましたが、まだ日中は暑い日が続きます。皆様如何お過ごしでしょうか。
今年は隣国ギニアの山岳地帯で大量の降水があったせいで、セネガル河中流域で大規模な洪水が発生しました。日本のような傾斜が急な河川では洪水が起こっても比較的早期に水が引きますが、セネガルのような平地が続く地形では土壌が水を吸収しなければ水がなかなか引かないことがあります。セネガル河流域の農作物の収穫に影響が出ているようですが、どのくらい深刻な被害になるのか気になるところです。
因みに、セネガル政府は人工衛星も使って洪水の状況をフォローしています。Centre Suivi Ecologique という機関が衛星画像を提供していますが、西アフリカ地域でこうした能力を有するのはセネガルだけだと思います。
10月はセネガルの発展への日本の協力の観点で重要なイベントが続きました。
先ず、11日に、CFPTにおいて、JICAの田中理事長やソンコ首相の出席を得て、CFPTの40周年記念式典とセック前代表に対する叙勲式が行われました。先月の挨拶でも書きましたが、40年にわたるCFPTの活動は人材育成を重視する我が国の経済協力の代表例です。本使は様々な機会に、天然資源の乏しい日本は人的資源を最大限活用して国を発展させてきたが、こうした日本の発展は多くのアフリカ諸国の発展のモデルになり得ると述べてきました。CFPTでの式典で、ソンコ首相が、人材を重視して国を興した日本はセネガルの発展のモデルになると力強く主張されたので、正に我が意を得たと嬉しく思いました。
17日には、ジョップ産業通商大臣が、ジャムナジョの国際会議場において、セネガルの産業振興のための戦略会議(Etats Generaux)を開催しました。本使は開会式のゲストスピーカーとして登壇し、そこでも人材育成の重要性を強調し、CFPTの分校をジャムナジョに建設する計画を紹介したところ、会場から大きな拍手を頂きました。ジョップ大臣は、日本の経済発展、特に経済産業省の業績をよく研究していて、日本の経済発展の経験を参考にしたい常から述べています。彼は大阪万博のセネガルの代表でもあるので、大臣とはこれからも緊密に連携していこうと考えています。
更に、29日には、ダカール大学で「JICAチェア」が開催され、京都大学の高橋アフリカ研究所長が昨年に引き続き講演し、今回は明治時代からの我が国の発展における西洋の技術の導入と日本の伝統技術の活用との関係について、米作の振興を例に取りながら話をされました。セネガルは国をあげて米の自給率を引きあげるために努力しているので、先生の話はセネガルの人々にとって大いに参考になったと思います。会場でも聴衆から多くの質問が出されました。
一つ嬉しい報告をします。
本使としては、大使館の活動をセネガル内外の皆様に広く知ってもらうことが重要だと考えてSNSを通じた広報に力を入れてます。その一環で、本使が着任してから大使館のホームページにおいてFacebookを本格的に立ちあげ大使館の活動等を広報してきましたが、上記のCFPTでの式典の模様を報じたところ、一気に500名の新規登録があり登録者数が5000人に近づきました。本年中に5000人を超えることは確実です。日本とセネガルは距離があり、日本においてセネガルの知名度はそれ程高くはありませんが、それでも5千人の方々が大使館の活動、更には日セネガル関係に関心をもってフォローしてくれているということは大使館にとって大きな励みになります。
そしてこのメルマガも広報活動の一つですが、今回、エドナさんと藤岡さんに寄稿して頂きました。いつもは大使館が寄稿者を選んでお願いしているのですが、今回、藤岡さんはこのメルマガの存在を知って、自分たちの活動を紹介したいので是非寄稿させて欲しいとの申し出がありました。こうした提案は大歓迎ですので、自分たちの活動を紹介したいという方がいましたら気軽に大使館に連絡してください。
最後に、セネガルの国民議会選挙については既に選挙活動が始まっており、一部支持者同士の衝突があるようですが今のところ大きな混乱も無く進んでいます。17日に投票が行われます。選挙について予断することは慎みますが、どのような結果になろうとも、日本政府は選挙で表明されるセネガル国民の民意を尊重してセネガル政府と協力していく所存です。
2 大使館からのお知らせ
○2024年11月、12月の休館日のお知らせ
11月1日 万聖節
12月25日 クリスマス
12月30、31日 年末休暇
3 寄稿1 ~エドナ・デュマ スペース・アン・ギャラリー代表~
日本とセネガルの架け橋としての芸術:スペース・アンとの旅
6年以上前、私は、豊かで洗練された文化に魅了され、日本に移住するという大胆な選択をしました。東京を拠点とするスペース・アン・ギャラリーの創設者として、在セネガル日本大使館のメールマガジンへの寄稿を通じて、私の経歴を紹介できることをとても光栄に思います。このような機会を通じて、私のキャリアを振り返ることができると同時に、日本とセネガルの豊かで多様な文化世界をつなぐ架け橋として、芸術が果たす役割の重要性を改めて実感することができます。
(1)幼少時代からの芸術への情熱
芸術は私の人生に欠かせないものであり、幼い頃からとても好きでした。成長するにつれ、芸術は単なる美的創造をはるかに超えた普遍的な言語であり、人間の魂を映し出す鏡であることを知るようになりました。芸術には、文化を表現し、深い感情を解き放ち、私たちの出自にかかわらず、人を結びつける独特の力があります。私にとり芸術とは、社会を貫く思想、希望、夢の具体的な表現形態なのです。
芸術は新たな発見へ誘ってくれるものでもあります。表面的なものを超えて物事を観察し、差異の美しさを受け入れる機会であります。グローバル化が進むこの世界において、芸術は他者との共通点を見出しながら、誰もが自分の個性を表現できるような求心力を持ちます。
(2)スペース・アンの開設:ひとつのギャラリー、ひとつの夢
スペース・アンは、地理的な境界を越え、多様な表現を行うことで文化が出会う場を創るというビジョンから生まれました。東京の中心に位置するこのギャラリーは、単なる展示スペースではありません。アフリカとアジアを結ぶ交差点であり、さらに広くは世界の異文化間の交差点でもあります。スペース・アンの神髄は、人々をつなぐ架け橋であり、一見かけ離れているように見えるものの、実際には多くの共通点を持つ芸術的感性が出会う場を提供することにあります。
スペース・アン・ギャラリーの正式な開設は、セネガルの偉大なアーティスト、アリウ・ジャロ氏の展覧会によってなされました。セネガルと日本の友好と深い絆を祝うものでした。アフリカの歴史と象徴主義に彩られたアリウ・ジャロ氏の作品は日本の人々を魅了し、芸術が異なる世界を結びつける強力な手段であることを示しました。
この最初の展覧会に続き、セネガル系フランス人アーティストのデルフィーヌ・ジャロ女史が、アイデンティティ、精神性、アフリカン・ディアスポラの問題を探求する作品を発表しました。力強くも内省的な彼女の作品は、東京の観客の心にも響き、芸術が相互理解や他者受容の扉を開くことができるということを再確認しました。
(3)日本とセネガル:芸術を通じた文化の対話
日本とセネガルは、豊かな伝統と革新性を併せ持つ国です。両国の関係は絶えることなく発展してきており、芸術はそこで基本的な役割を果たしています。両国の文化交流には、意外な共通点が見られることがよくあります。例えば、セネガルの伝統的な織物や日本の陶芸・木工など、両国は工芸品に重要な価値を置いており、両国が手作業や芸術表現に対する深い敬意を示していることがわかります。
スペース・アンを通じて私が常に心がけているのは、相違点を大切にしながら共通点を浮き彫りにすることです。芸術は美を表現する手段であるだけでなく、現代の問題を考える手段でもあります。このギャラリーの創設者である私の役割は、異なる背景を持つアーティスト同士の対話を促し、交流と驚きを誘発する展覧会を提供することです。
(4)このメールマガジンに寄稿できる光栄
在セネガル日本大使館からこのメールマガジンへの寄稿を依頼されたとき、大変光栄に思いました。このような機会をいただけたことで、私の人生においても仕事においても大切なこの2か国のすぐれた関係を強調することができます。私は自分のギャラリーにおいて芸術的協力を進めることで日セネガル関係を前進させようと努めており、芸術が文化間の結びつきを強めるのに役立つと確信しています。
私は、芸術が変化をもたらしてくれるきっかけになると信じています。芸術は、私たちが違いを超え、理解し、受け入れることを可能にしてくれるのです。スペース・アンの創設者である私の個人的な旅は、この大胆な取り組みの一部です。日本での生活では、自分の出自に深く根ざしつつも、その文化のニュアンスを観察し、理解することを学びました。この2つの世界の交差点に立つことで、私は文化の多様性を積極的に需要することの重要性に気づきました。
(5)スペース・アン:未来へのプラットフォーム
スペース・アンの目的は、大陸間、特にアフリカとアジアの間の対話を拡大し、多様な背景を持つアーティストがアイデアを交換し、物語を共有し、世界にインスピレーションを与えることができるような場を作ることです。展覧会、アーティストの滞在、文化イベントなどを行うことで、スペース・アンは人々の出会いの場となります。私たちは、来場者に異なる視点に立って多様な形態の芸術を鑑賞してもらい、そして何よりも文化の違いからインスピレーションを得る機会を提供します。
このプラットフォームを通じて、アーティスト、コレクター、美術愛好家の方々に、芸術表現が国境や言語の壁を超える場になることを願っています。こうして芸術は、多様性の中の統一を促していく普遍的な言語となっていきます。
(6)おわりに
最後に、このメールマガジンで私とスペース・アンの背景を紹介する機会をいただき、深く感謝しています。私にとって芸術は、コミュニティを結びつけ、相互理解を促し、調和を促進する最も効果的な方法のひとつです。私はスペース・アンを通じて、芸術が文化間の対話の手段となるよう、特に日本とセネガルという、違いはあっても人間性と創造性という共通のビジョンを持つ国同士の対話の手段となるよう、努力を続けていきます。
本誌に寄稿する機会を与えていただきありがとうございました。スペース・アンが、これからもこの2つの素晴らしい文化にインスピレーションを与え、その結びつきを強めていくことを願っています。
寄稿2 ~藤岡幸絵 UNDPガンビア事務所・平和構築専門官 (国連ボランティア)~ (前編)※後編は12月号でお届けします。
はじめまして!国連開発計画(UNDP)ガンビア事務所で平和構築専門官として活動している藤岡幸絵と申します。UNDPは、持続可能な開発、民主的なガバナンスと平和構築、気候変動と災害に対する強靭性の3つの柱に基づいて活動を行なっている国際機関です。日本とのつながりが深い活動の一つでは、アフリカ開発会議(TICAD)を外務省等とともに共催しています。先日開催されたTICAD閣僚会合のテーマ別会合では、アフリカと日本を繋ぐユースの一人として、ガンビアでの経験をお話する機会をいただきました(ご参考リンク:https://www.jica.go.jp/information/seminar/2024/1549305_52234.html)。
ガンビア事務所では、政府機関、市民社会、アカデミア、民間企業、他の国際機関など、多岐にわたるパートナーとともに、SDGsの推進及びガンビアの国家開発計画「イリワー」に基づいた優先分野に沿って活動しています。「イリワー」はマンディンカ語で「開発」の意味を持ちます。UNDPガンビア事務所は、包括的な経済発展、民主的なガバナンスと平和構築、気候変動と災害に対する強靭性の3つの柱に基づいて活動を行なっている他、Accerelator Lab を通じて、イノベーティブなアプローチによるユースの支援・エンパワメントなどを行なっています。UNDPガンビア事務所の活動については、X(https://x.com/undp_thegambia)もしくはFB(https://www.facebook.com/UNDPGambia)で発信をしていますので、もし良ければ合わせてご参照ください。
今回は私がどうして平和構築の分野を志すようになったのか、またガンビアという国そのものについてや平和構築との関連で発見したことについてご共有させていただければと思います。なお、以下の内容は私個人の見解であり、UNDPガンビアとしての公式な見解ではないことをあらかじめ補足させていただきます。
(1)普通の女子高生だった私が、平和構築でのキャリアを目指すまで
私は高校生くらいまで、海外とは無縁の人生を過ごしてきました。当時は部活に明け暮れていたのですが、はじめて未来のことを考えるきっかけになったのが、高校一年生の終わり頃に「進路選択」を考えたことです。元々、数学以外勉強がほぼできなかったものの、理系を選択した先の自分の人生が描けず、自分の好きなことに照らして考えた際に、唯一思いついたことが、ラテンアメリカのお洋服が好きで、海外からお洋服や手芸品を持ってくるバイヤーという仕事に就けたら面白いかもしれない、ということでした。安易な発想ですが、そんな理由で文系を選択した後に、外国の人と話したこともない自分が、果たしてラテンアメリカから買い付けなんてできるのか?という疑問を持ち、高校二年生の夏に国内で行われた国際交流のプログラムに参加しました。そのプログラムに参加して、多少言葉が通じなくても楽しい時間は共有できるものなのかなと感じていたところに、フィリピンからの参加者の友達が、実は元ストリートチルドレンだったということを知りました。目の前で友達が泣いているのに、言葉の不自由さと勉強不足が相まって、自分はまるでその友達の環境や状況が理解しきれていないのだとショックに感じ、言葉を知らなければ、世界のことを知らなければ、もしかしたら自分は周りの友達のことさえ理解できないのかもしれない、と考えたことで、社会課題なども含めてしっかり理解できる人になりたいと思うようになり、その後猛勉強の末に国際基督教大学という大学に入学しました。
入学時点では、国際協力の分野で働きたいという明確な意志はなかったものの、フィリピン人の友達に出会って自分のものの見方が大きく変わったことから「人と人が出会うこと、対話をすることから良い変化が生まれる可能性」を強く信じていたので、日本イスラエルパレスチナ学生会議という、紛争の当事者の若者を日本に招聘し紛争について腹を割って対話をする機会を作っている団体を知った際に興味を持ち、参加することにしました。この活動からパレスチナとイスラエルの双方に多数の友人ができ、今度は友達に会いたいという動機で現地を頻繁に訪問するようになり、次第にパレスチナの状況がひとごとではなくなっていきました。学部の卒業論文では、パレスチナ難民キャンプの中で1か月住み込みでアラビア語で調査をしました。パレスチナ難民のホストファミリーとともに暮らし、1日24時間難民キャンプの中で生活をする中で、パレスチナ難民の人々が直面する深刻な社会経済的困難を目の当たりにしました。
1993年の和平合意、オスロ合意が失敗してから現在も紛争が継続しており、パレスチナ情勢は厳しい状況にありますが、学生時代のさまざまな人との交流によって、紛争下において、脆弱な層の人が特に大きい犠牲を払っていると肌身を持って実感し、このような特に大きな犠牲を払っている人たちのために平和の恩恵を届けられたらいいのにと、平和構築の分野を志すようになりました。
(2)ガンビアでの暮らしについて
そこから様々な経験を経て、外務省の「平和構築・開発分野におけるグローバル人材育成事業」に採用いただき、国連ボランティアとしてUNDPガンビア事務所へ派遣されることになりました。仕事が連れてきてくれたガンビア “Smiling Coast of Africa”は、一歩外に出れば皆が話しかけてきてくれるとてもフレンドリーかつ親切な人が多い国で、乗合タクシーに乗って移動すると運転手の方から支払いは要らないよと言われたり、一緒に乗っている現地の人がなぜか私の乗車賃を払ってくれてしまったりするような、外国人に対してもとても優しい国です。ちなみに、首都圏の平均月収は約1000ダラシであるのに対し、運賃は片道13ダラシ。これは日本円にして約30円なので、奢られることが申し訳なく感じるところもありますが、いかにガンビアの人たちが優しいかを実感しています。オフィスに行けば、セキュリティスタッフから清掃員さん、ドライバーさんから他の国際機関のスタッフまで、皆笑顔で挨拶してくれますし、忙しそうにしていると心配そうに気遣って声をかけてくれたりもします。
そんなガンビアを好きになるのに、そう時間はかかりませんでした。お米を主食とした現地飯もとても美味しく、地方に行くと田園風景が広がっておりとても綺麗です。自然がとても豊かなガンビアは、国の真ん中をガンビア川が走っており、海に面しているため、農業や漁業、狩猟を生業とする人がいます。約600種類の鳥が生息していると言われており、私が住んでいる首都圏セレクンダにいても、エメラルドブルーやイエローの鳥などカラフルな鳥がたくさんいるので、ちょっとした用事でも外出するのがとても楽しいです。
(3)ガンビアにおける平和構築の歩み
ガンビアは、2016年の12月の選挙の結果、22年以上にわたる独裁政権が終焉を迎えた国で、現在も民主主義に基づいた平和への移行の最中にあります。前職では南スーダンにおいて女性や若者を平和の担い手として育成し、コミュニティレベルでの紛争解決の仕組みづくりに関わっていたのですが(ご参考:前職の上司が外務省の動画で特集された際のリンク・当方も一部映っていますhttps://www.youtube.com/watch?v=ytfXnMYbuwE)、直近の南スーダンも含めて、これまで複数のステークホルダーが相容れない利害関係の元に対立しているような文脈における平和構築のケースに関わることが多かったため、独裁政権の終焉後、民主化への道をたどっているような国における平和構築の取り組みに携わることはとても印象深いものがあります。
独裁政権の終焉後、独裁政権下で起こっていた人権侵害を明らかにし、暗殺等について真実を特定するため「真実、和解及び賠償委員会(通称TRRC)」が設置され、多くの人からの証言を集めるなど徹底した事実特定が行われたのちに、独裁政権下で起こっていたことを包括的に取り纏めた報告書「Never Again Report」が2021年末に最終化されました。現政権がこの報告書の内容を読み、提言のほぼ全てを受け入れることを約束したことで、政府として正式に過去の国の過ちを認め、二度と同じ過ちを繰り返さないことを宣言したのです。私が今携わっている事業は、まさに、現政権が過去の過ちを二度と繰り返さないための提言として記載されている「平和構築・紛争解決の仕組みづくり」の実現に向けた支援を行っています。具体的には、平和構築に関連する政策策定の支援や、ガンビアにある不安定要因の分析(Conflict and Development Analysis)支援、いち早く紛争の予兆を特定し早く紛争の種を摘むことができるよう対応する仕組みの強化(早期警戒早期対応システム)、平和構築を主管する国家機関の立ち上げや国内の治安維持を主管している内務省への能力強化支援、コミュニティレベルでの紛争解決の担い手の育成など、平和構築・紛争解決の仕組みづくりを国レベル、地域レベル、コミュニティレベルの様々な階層で包括的に推進しています。
(後編へ続く)
4 領事便り
○ 在外選挙の終了について
第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)について、当館においては10月16日(水)から19日(土)までの4日間を在外選挙期間として実施させていただきました。
同期間中には多数の方に投票をいただき、また、大きな事故もなく無事国内に投票を引き継ぎ国内においても集計が終了しております。
最高裁判所裁判官国民審査の在外公館での実施については、今次の選挙が初となり今後増加が想定される海外赴任者の公民権の行使についても見直しが図られた有意義な選挙であったと感じております。
また、今後の在外選挙についても事前広報をさせていただきますのでご参加の程どうぞよろしくお願いいたします。
投票に必要なもの:在外選挙人証、旅券等の身分証明書
5 政治・経済
○伊澤大使及び田中JICA理事長によるファイ大統領表敬
10月10日、伊澤大使は、当地訪問中の田中JICA理事長と共にファイ大統領を表敬訪問し、両国の協力関係の更なる強化に向けた方途について意見交換しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01526.html
○セネガル・日本職業訓練センター(CFPT Sénégal-Japon)40周年記念式典の開催
10月11日、セネガル・日本職業訓練センターで、ソンコ首相の主宰で同センター40周年記念式典が開催され、サレ職業訓練大臣、伊澤大使、田中JICA理事長はじめ多くの関係者が出席しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01524.html
○ババカール・セック前セネガル・日本職業訓練センター(CFPT)校長への旭日双光章伝達式の開催
10月11日、日本職業訓練センター(CFPT)において、同センターの40周年記念式典に先立ち、令和6年春の外国人叙勲の対象者であるババカール・セック前CFPT校長への旭日双光章 の伝達式が開催され、ソンコ首相 らセネガル政府要人、JICA田中理事長、同セネガル事務所代表等が参加しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01522.html
○日本企業連絡会の開催
10月11日、伊澤大使は、当地訪問中の田中JICA理事長の同席の下、日本企業連絡会を開催し、セネガルにおける各社の活動や今後の見通しについて意見交換しました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034kzv7ygeZc87th3bFFHkmiSxx6863Yejiawqn1uNeeHaKRen4YNgLyDEYXDQ6kJLl&id=100078921276471
○セネガル産業・通商省主催「産業・通商・中小企業・中小製造業戦略会議」への出席
17日、伊澤大使は、セネガル産業・通商省主催「産業・通商・中小企業・中小製造業戦略会議」において登壇し、セネガルの産業発展に向けて、戦略、人材育成およびセネガルの宣伝が重要である旨を強調しました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0paRrsUHDg63HnStXDr6p7wWxCprbUeXPjw1MSVJjANMMbAXNn1ZYDgBAXM4FDD6Tl&id=100078921276471
○在外公館長表彰式:パパ・マガトゥ・ゲイ日セネガル友好協会(ASENI)会長への伝達式の実施
10月19日、パパ・マガトゥ・ゲイ日セネガル友好協会(ASENI)会長に対し、伊澤大使から、日セネガル関係強化への貢献を称え、在外公館長表彰が授与されました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01532.html
○伊澤大使によるジョップ国防大臣表敬
10月24日、伊澤大使は、ジョップ国防大臣を表敬し、我が国がカザマンス地方で実施する地雷除去活動支援について意見交換しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01543.html
○伊澤大使によるJICAチェアへの参加
10月29日、ダカール大学(UCAD)において、JICAセネガル事務所主催で日本の発展の教訓をテーマにするJICAチェアが開催されました。伊澤大使は京都大学の高橋基樹教授とともに参加しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01545.html
○JETROアフリカビジネスデスク
ジェトロ(日本貿易振興機構)は、アフリカでの事業展開を目指す法人及びアフリカですでに事業を展開している法人を対象に相談サービスを提供しています。
対象国は20か国で、セネガルも対象国に含まれていますので、活用をご検討ください。
【詳細】
https://www.jetro.go.jp/services/africa_bizdesk.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3vePD6Ntz0xjeO_a3yCxw3b_An2F6r7apxSQiUKG-mzCYiKcNYm7xnQmc_aem_fgnxm1eyZLBAn6WZF5me2A
○当館が所掌する4か国(セネガル、カーボベルデ、ガンビア、ギニアビサウ)の政治経済関連の一般情報は、毎月上旬に当館のHP「セネガル基礎情報」及び「新着情報」に「在セネガル大使館月例報告」として掲載しております。ご関心のある方は以下のリンクをご参照ください。
(参考)月例報告:https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01078.html
6 広報・文化便り
○第37回俳句コンクール作品募集開始
在セネガル日本大使館はこの度、第37回俳句コンクールの作品募集を開始しました。概要は以下のリンクのとおりです。どなたでも応募いただけますので、みなさまの作品をお待ちしております。
応募期限:2024年12月20日
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01535.html
○セネガル柔道連盟主催「2024年柔道日本大使杯」の開催
10月26日、ダカール市内のマリウス・ンジャイ・スタジアム(Stade Marius Ndiaye)にて、セネガル柔道連盟の主催により「2024年柔道日本国大使杯」が開催されました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01541.html
○「2024年空手大使杯」の開催
11月30日、「2024年空手大使杯」が以下のとおり開催されます。どなたでも見学できるため、関心のある方はご覧ください。
日時:11月30日(土) 16時ごろから各階級の決勝戦が始まります。
会場:Stade Marius Ndiaye
○当館では、日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本関連行事のほか、知り合いの方のご活動等についての情報を( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )までお知らせください。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。当館HPやSNSへの掲載は随時行います。
○当館SNSでは、セネガルで開催されるイベントの告知や当館の活動報告を行っています。他にもたくさんのコンテンツがありますので、定期的にアクセスしてみてください。また、日・セネガル関係強化のため、ご関心のある投稿のRTやシェア等、皆さまのご協力をぜひお願いいたします。
TW:https://twitter.com/JapanEmbSenegal
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471
Instagram:https://www.instagram.com/japanembsenegal/
----------------------------------------------------------------------
[在セネガル日本大使館メールマガジン]
○本メールマガジンに関するご意見・ご要望は以下のメールアドレスあてに送信してください。新規配信登録のご希望もこちらまでお寄せください。
( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )
○参考ホームページ
首相官邸ホームページ ( www.kantei.go.jp )
外務省ホームページ ( www.mofa.go.jp/mofaj/ )
当館ホームページ ( https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
○発行:在セネガル日本大使館
Ambassade du Japon au Senegal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Senegal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55
◆ 目次 ◆
1 「伊澤修駐セネガル日本大使挨拶」
2 「大使館からのお知らせ」
3 「寄稿文」
4 「領事便り」
5 「政治・経済」
6 「広報・文化便り」
***********************
1 伊澤修駐セネガル日本大使挨拶
10月後半からは乾期に入りましたが、まだ日中は暑い日が続きます。皆様如何お過ごしでしょうか。
今年は隣国ギニアの山岳地帯で大量の降水があったせいで、セネガル河中流域で大規模な洪水が発生しました。日本のような傾斜が急な河川では洪水が起こっても比較的早期に水が引きますが、セネガルのような平地が続く地形では土壌が水を吸収しなければ水がなかなか引かないことがあります。セネガル河流域の農作物の収穫に影響が出ているようですが、どのくらい深刻な被害になるのか気になるところです。
因みに、セネガル政府は人工衛星も使って洪水の状況をフォローしています。Centre Suivi Ecologique という機関が衛星画像を提供していますが、西アフリカ地域でこうした能力を有するのはセネガルだけだと思います。
10月はセネガルの発展への日本の協力の観点で重要なイベントが続きました。
先ず、11日に、CFPTにおいて、JICAの田中理事長やソンコ首相の出席を得て、CFPTの40周年記念式典とセック前代表に対する叙勲式が行われました。先月の挨拶でも書きましたが、40年にわたるCFPTの活動は人材育成を重視する我が国の経済協力の代表例です。本使は様々な機会に、天然資源の乏しい日本は人的資源を最大限活用して国を発展させてきたが、こうした日本の発展は多くのアフリカ諸国の発展のモデルになり得ると述べてきました。CFPTでの式典で、ソンコ首相が、人材を重視して国を興した日本はセネガルの発展のモデルになると力強く主張されたので、正に我が意を得たと嬉しく思いました。
17日には、ジョップ産業通商大臣が、ジャムナジョの国際会議場において、セネガルの産業振興のための戦略会議(Etats Generaux)を開催しました。本使は開会式のゲストスピーカーとして登壇し、そこでも人材育成の重要性を強調し、CFPTの分校をジャムナジョに建設する計画を紹介したところ、会場から大きな拍手を頂きました。ジョップ大臣は、日本の経済発展、特に経済産業省の業績をよく研究していて、日本の経済発展の経験を参考にしたい常から述べています。彼は大阪万博のセネガルの代表でもあるので、大臣とはこれからも緊密に連携していこうと考えています。
更に、29日には、ダカール大学で「JICAチェア」が開催され、京都大学の高橋アフリカ研究所長が昨年に引き続き講演し、今回は明治時代からの我が国の発展における西洋の技術の導入と日本の伝統技術の活用との関係について、米作の振興を例に取りながら話をされました。セネガルは国をあげて米の自給率を引きあげるために努力しているので、先生の話はセネガルの人々にとって大いに参考になったと思います。会場でも聴衆から多くの質問が出されました。
一つ嬉しい報告をします。
本使としては、大使館の活動をセネガル内外の皆様に広く知ってもらうことが重要だと考えてSNSを通じた広報に力を入れてます。その一環で、本使が着任してから大使館のホームページにおいてFacebookを本格的に立ちあげ大使館の活動等を広報してきましたが、上記のCFPTでの式典の模様を報じたところ、一気に500名の新規登録があり登録者数が5000人に近づきました。本年中に5000人を超えることは確実です。日本とセネガルは距離があり、日本においてセネガルの知名度はそれ程高くはありませんが、それでも5千人の方々が大使館の活動、更には日セネガル関係に関心をもってフォローしてくれているということは大使館にとって大きな励みになります。
そしてこのメルマガも広報活動の一つですが、今回、エドナさんと藤岡さんに寄稿して頂きました。いつもは大使館が寄稿者を選んでお願いしているのですが、今回、藤岡さんはこのメルマガの存在を知って、自分たちの活動を紹介したいので是非寄稿させて欲しいとの申し出がありました。こうした提案は大歓迎ですので、自分たちの活動を紹介したいという方がいましたら気軽に大使館に連絡してください。
最後に、セネガルの国民議会選挙については既に選挙活動が始まっており、一部支持者同士の衝突があるようですが今のところ大きな混乱も無く進んでいます。17日に投票が行われます。選挙について予断することは慎みますが、どのような結果になろうとも、日本政府は選挙で表明されるセネガル国民の民意を尊重してセネガル政府と協力していく所存です。
2 大使館からのお知らせ
○2024年11月、12月の休館日のお知らせ
11月1日 万聖節
12月25日 クリスマス
12月30、31日 年末休暇
3 寄稿1 ~エドナ・デュマ スペース・アン・ギャラリー代表~
日本とセネガルの架け橋としての芸術:スペース・アンとの旅
6年以上前、私は、豊かで洗練された文化に魅了され、日本に移住するという大胆な選択をしました。東京を拠点とするスペース・アン・ギャラリーの創設者として、在セネガル日本大使館のメールマガジンへの寄稿を通じて、私の経歴を紹介できることをとても光栄に思います。このような機会を通じて、私のキャリアを振り返ることができると同時に、日本とセネガルの豊かで多様な文化世界をつなぐ架け橋として、芸術が果たす役割の重要性を改めて実感することができます。
(1)幼少時代からの芸術への情熱
芸術は私の人生に欠かせないものであり、幼い頃からとても好きでした。成長するにつれ、芸術は単なる美的創造をはるかに超えた普遍的な言語であり、人間の魂を映し出す鏡であることを知るようになりました。芸術には、文化を表現し、深い感情を解き放ち、私たちの出自にかかわらず、人を結びつける独特の力があります。私にとり芸術とは、社会を貫く思想、希望、夢の具体的な表現形態なのです。
芸術は新たな発見へ誘ってくれるものでもあります。表面的なものを超えて物事を観察し、差異の美しさを受け入れる機会であります。グローバル化が進むこの世界において、芸術は他者との共通点を見出しながら、誰もが自分の個性を表現できるような求心力を持ちます。
(2)スペース・アンの開設:ひとつのギャラリー、ひとつの夢
スペース・アンは、地理的な境界を越え、多様な表現を行うことで文化が出会う場を創るというビジョンから生まれました。東京の中心に位置するこのギャラリーは、単なる展示スペースではありません。アフリカとアジアを結ぶ交差点であり、さらに広くは世界の異文化間の交差点でもあります。スペース・アンの神髄は、人々をつなぐ架け橋であり、一見かけ離れているように見えるものの、実際には多くの共通点を持つ芸術的感性が出会う場を提供することにあります。
スペース・アン・ギャラリーの正式な開設は、セネガルの偉大なアーティスト、アリウ・ジャロ氏の展覧会によってなされました。セネガルと日本の友好と深い絆を祝うものでした。アフリカの歴史と象徴主義に彩られたアリウ・ジャロ氏の作品は日本の人々を魅了し、芸術が異なる世界を結びつける強力な手段であることを示しました。
この最初の展覧会に続き、セネガル系フランス人アーティストのデルフィーヌ・ジャロ女史が、アイデンティティ、精神性、アフリカン・ディアスポラの問題を探求する作品を発表しました。力強くも内省的な彼女の作品は、東京の観客の心にも響き、芸術が相互理解や他者受容の扉を開くことができるということを再確認しました。
(3)日本とセネガル:芸術を通じた文化の対話
日本とセネガルは、豊かな伝統と革新性を併せ持つ国です。両国の関係は絶えることなく発展してきており、芸術はそこで基本的な役割を果たしています。両国の文化交流には、意外な共通点が見られることがよくあります。例えば、セネガルの伝統的な織物や日本の陶芸・木工など、両国は工芸品に重要な価値を置いており、両国が手作業や芸術表現に対する深い敬意を示していることがわかります。
スペース・アンを通じて私が常に心がけているのは、相違点を大切にしながら共通点を浮き彫りにすることです。芸術は美を表現する手段であるだけでなく、現代の問題を考える手段でもあります。このギャラリーの創設者である私の役割は、異なる背景を持つアーティスト同士の対話を促し、交流と驚きを誘発する展覧会を提供することです。
(4)このメールマガジンに寄稿できる光栄
在セネガル日本大使館からこのメールマガジンへの寄稿を依頼されたとき、大変光栄に思いました。このような機会をいただけたことで、私の人生においても仕事においても大切なこの2か国のすぐれた関係を強調することができます。私は自分のギャラリーにおいて芸術的協力を進めることで日セネガル関係を前進させようと努めており、芸術が文化間の結びつきを強めるのに役立つと確信しています。
私は、芸術が変化をもたらしてくれるきっかけになると信じています。芸術は、私たちが違いを超え、理解し、受け入れることを可能にしてくれるのです。スペース・アンの創設者である私の個人的な旅は、この大胆な取り組みの一部です。日本での生活では、自分の出自に深く根ざしつつも、その文化のニュアンスを観察し、理解することを学びました。この2つの世界の交差点に立つことで、私は文化の多様性を積極的に需要することの重要性に気づきました。
(5)スペース・アン:未来へのプラットフォーム
スペース・アンの目的は、大陸間、特にアフリカとアジアの間の対話を拡大し、多様な背景を持つアーティストがアイデアを交換し、物語を共有し、世界にインスピレーションを与えることができるような場を作ることです。展覧会、アーティストの滞在、文化イベントなどを行うことで、スペース・アンは人々の出会いの場となります。私たちは、来場者に異なる視点に立って多様な形態の芸術を鑑賞してもらい、そして何よりも文化の違いからインスピレーションを得る機会を提供します。
このプラットフォームを通じて、アーティスト、コレクター、美術愛好家の方々に、芸術表現が国境や言語の壁を超える場になることを願っています。こうして芸術は、多様性の中の統一を促していく普遍的な言語となっていきます。
(6)おわりに
最後に、このメールマガジンで私とスペース・アンの背景を紹介する機会をいただき、深く感謝しています。私にとって芸術は、コミュニティを結びつけ、相互理解を促し、調和を促進する最も効果的な方法のひとつです。私はスペース・アンを通じて、芸術が文化間の対話の手段となるよう、特に日本とセネガルという、違いはあっても人間性と創造性という共通のビジョンを持つ国同士の対話の手段となるよう、努力を続けていきます。
本誌に寄稿する機会を与えていただきありがとうございました。スペース・アンが、これからもこの2つの素晴らしい文化にインスピレーションを与え、その結びつきを強めていくことを願っています。
寄稿2 ~藤岡幸絵 UNDPガンビア事務所・平和構築専門官 (国連ボランティア)~ (前編)※後編は12月号でお届けします。
はじめまして!国連開発計画(UNDP)ガンビア事務所で平和構築専門官として活動している藤岡幸絵と申します。UNDPは、持続可能な開発、民主的なガバナンスと平和構築、気候変動と災害に対する強靭性の3つの柱に基づいて活動を行なっている国際機関です。日本とのつながりが深い活動の一つでは、アフリカ開発会議(TICAD)を外務省等とともに共催しています。先日開催されたTICAD閣僚会合のテーマ別会合では、アフリカと日本を繋ぐユースの一人として、ガンビアでの経験をお話する機会をいただきました(ご参考リンク:https://www.jica.go.jp/information/seminar/2024/1549305_52234.html)。
ガンビア事務所では、政府機関、市民社会、アカデミア、民間企業、他の国際機関など、多岐にわたるパートナーとともに、SDGsの推進及びガンビアの国家開発計画「イリワー」に基づいた優先分野に沿って活動しています。「イリワー」はマンディンカ語で「開発」の意味を持ちます。UNDPガンビア事務所は、包括的な経済発展、民主的なガバナンスと平和構築、気候変動と災害に対する強靭性の3つの柱に基づいて活動を行なっている他、Accerelator Lab を通じて、イノベーティブなアプローチによるユースの支援・エンパワメントなどを行なっています。UNDPガンビア事務所の活動については、X(https://x.com/undp_thegambia)もしくはFB(https://www.facebook.com/UNDPGambia)で発信をしていますので、もし良ければ合わせてご参照ください。
今回は私がどうして平和構築の分野を志すようになったのか、またガンビアという国そのものについてや平和構築との関連で発見したことについてご共有させていただければと思います。なお、以下の内容は私個人の見解であり、UNDPガンビアとしての公式な見解ではないことをあらかじめ補足させていただきます。
(1)普通の女子高生だった私が、平和構築でのキャリアを目指すまで
私は高校生くらいまで、海外とは無縁の人生を過ごしてきました。当時は部活に明け暮れていたのですが、はじめて未来のことを考えるきっかけになったのが、高校一年生の終わり頃に「進路選択」を考えたことです。元々、数学以外勉強がほぼできなかったものの、理系を選択した先の自分の人生が描けず、自分の好きなことに照らして考えた際に、唯一思いついたことが、ラテンアメリカのお洋服が好きで、海外からお洋服や手芸品を持ってくるバイヤーという仕事に就けたら面白いかもしれない、ということでした。安易な発想ですが、そんな理由で文系を選択した後に、外国の人と話したこともない自分が、果たしてラテンアメリカから買い付けなんてできるのか?という疑問を持ち、高校二年生の夏に国内で行われた国際交流のプログラムに参加しました。そのプログラムに参加して、多少言葉が通じなくても楽しい時間は共有できるものなのかなと感じていたところに、フィリピンからの参加者の友達が、実は元ストリートチルドレンだったということを知りました。目の前で友達が泣いているのに、言葉の不自由さと勉強不足が相まって、自分はまるでその友達の環境や状況が理解しきれていないのだとショックに感じ、言葉を知らなければ、世界のことを知らなければ、もしかしたら自分は周りの友達のことさえ理解できないのかもしれない、と考えたことで、社会課題なども含めてしっかり理解できる人になりたいと思うようになり、その後猛勉強の末に国際基督教大学という大学に入学しました。
入学時点では、国際協力の分野で働きたいという明確な意志はなかったものの、フィリピン人の友達に出会って自分のものの見方が大きく変わったことから「人と人が出会うこと、対話をすることから良い変化が生まれる可能性」を強く信じていたので、日本イスラエルパレスチナ学生会議という、紛争の当事者の若者を日本に招聘し紛争について腹を割って対話をする機会を作っている団体を知った際に興味を持ち、参加することにしました。この活動からパレスチナとイスラエルの双方に多数の友人ができ、今度は友達に会いたいという動機で現地を頻繁に訪問するようになり、次第にパレスチナの状況がひとごとではなくなっていきました。学部の卒業論文では、パレスチナ難民キャンプの中で1か月住み込みでアラビア語で調査をしました。パレスチナ難民のホストファミリーとともに暮らし、1日24時間難民キャンプの中で生活をする中で、パレスチナ難民の人々が直面する深刻な社会経済的困難を目の当たりにしました。
1993年の和平合意、オスロ合意が失敗してから現在も紛争が継続しており、パレスチナ情勢は厳しい状況にありますが、学生時代のさまざまな人との交流によって、紛争下において、脆弱な層の人が特に大きい犠牲を払っていると肌身を持って実感し、このような特に大きな犠牲を払っている人たちのために平和の恩恵を届けられたらいいのにと、平和構築の分野を志すようになりました。
(2)ガンビアでの暮らしについて
そこから様々な経験を経て、外務省の「平和構築・開発分野におけるグローバル人材育成事業」に採用いただき、国連ボランティアとしてUNDPガンビア事務所へ派遣されることになりました。仕事が連れてきてくれたガンビア “Smiling Coast of Africa”は、一歩外に出れば皆が話しかけてきてくれるとてもフレンドリーかつ親切な人が多い国で、乗合タクシーに乗って移動すると運転手の方から支払いは要らないよと言われたり、一緒に乗っている現地の人がなぜか私の乗車賃を払ってくれてしまったりするような、外国人に対してもとても優しい国です。ちなみに、首都圏の平均月収は約1000ダラシであるのに対し、運賃は片道13ダラシ。これは日本円にして約30円なので、奢られることが申し訳なく感じるところもありますが、いかにガンビアの人たちが優しいかを実感しています。オフィスに行けば、セキュリティスタッフから清掃員さん、ドライバーさんから他の国際機関のスタッフまで、皆笑顔で挨拶してくれますし、忙しそうにしていると心配そうに気遣って声をかけてくれたりもします。
そんなガンビアを好きになるのに、そう時間はかかりませんでした。お米を主食とした現地飯もとても美味しく、地方に行くと田園風景が広がっておりとても綺麗です。自然がとても豊かなガンビアは、国の真ん中をガンビア川が走っており、海に面しているため、農業や漁業、狩猟を生業とする人がいます。約600種類の鳥が生息していると言われており、私が住んでいる首都圏セレクンダにいても、エメラルドブルーやイエローの鳥などカラフルな鳥がたくさんいるので、ちょっとした用事でも外出するのがとても楽しいです。
(3)ガンビアにおける平和構築の歩み
ガンビアは、2016年の12月の選挙の結果、22年以上にわたる独裁政権が終焉を迎えた国で、現在も民主主義に基づいた平和への移行の最中にあります。前職では南スーダンにおいて女性や若者を平和の担い手として育成し、コミュニティレベルでの紛争解決の仕組みづくりに関わっていたのですが(ご参考:前職の上司が外務省の動画で特集された際のリンク・当方も一部映っていますhttps://www.youtube.com/watch?v=ytfXnMYbuwE)、直近の南スーダンも含めて、これまで複数のステークホルダーが相容れない利害関係の元に対立しているような文脈における平和構築のケースに関わることが多かったため、独裁政権の終焉後、民主化への道をたどっているような国における平和構築の取り組みに携わることはとても印象深いものがあります。
独裁政権の終焉後、独裁政権下で起こっていた人権侵害を明らかにし、暗殺等について真実を特定するため「真実、和解及び賠償委員会(通称TRRC)」が設置され、多くの人からの証言を集めるなど徹底した事実特定が行われたのちに、独裁政権下で起こっていたことを包括的に取り纏めた報告書「Never Again Report」が2021年末に最終化されました。現政権がこの報告書の内容を読み、提言のほぼ全てを受け入れることを約束したことで、政府として正式に過去の国の過ちを認め、二度と同じ過ちを繰り返さないことを宣言したのです。私が今携わっている事業は、まさに、現政権が過去の過ちを二度と繰り返さないための提言として記載されている「平和構築・紛争解決の仕組みづくり」の実現に向けた支援を行っています。具体的には、平和構築に関連する政策策定の支援や、ガンビアにある不安定要因の分析(Conflict and Development Analysis)支援、いち早く紛争の予兆を特定し早く紛争の種を摘むことができるよう対応する仕組みの強化(早期警戒早期対応システム)、平和構築を主管する国家機関の立ち上げや国内の治安維持を主管している内務省への能力強化支援、コミュニティレベルでの紛争解決の担い手の育成など、平和構築・紛争解決の仕組みづくりを国レベル、地域レベル、コミュニティレベルの様々な階層で包括的に推進しています。
(後編へ続く)
4 領事便り
○ 在外選挙の終了について
第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手県選挙区)について、当館においては10月16日(水)から19日(土)までの4日間を在外選挙期間として実施させていただきました。
同期間中には多数の方に投票をいただき、また、大きな事故もなく無事国内に投票を引き継ぎ国内においても集計が終了しております。
最高裁判所裁判官国民審査の在外公館での実施については、今次の選挙が初となり今後増加が想定される海外赴任者の公民権の行使についても見直しが図られた有意義な選挙であったと感じております。
また、今後の在外選挙についても事前広報をさせていただきますのでご参加の程どうぞよろしくお願いいたします。
投票に必要なもの:在外選挙人証、旅券等の身分証明書
5 政治・経済
○伊澤大使及び田中JICA理事長によるファイ大統領表敬
10月10日、伊澤大使は、当地訪問中の田中JICA理事長と共にファイ大統領を表敬訪問し、両国の協力関係の更なる強化に向けた方途について意見交換しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01526.html
○セネガル・日本職業訓練センター(CFPT Sénégal-Japon)40周年記念式典の開催
10月11日、セネガル・日本職業訓練センターで、ソンコ首相の主宰で同センター40周年記念式典が開催され、サレ職業訓練大臣、伊澤大使、田中JICA理事長はじめ多くの関係者が出席しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01524.html
○ババカール・セック前セネガル・日本職業訓練センター(CFPT)校長への旭日双光章伝達式の開催
10月11日、日本職業訓練センター(CFPT)において、同センターの40周年記念式典に先立ち、令和6年春の外国人叙勲の対象者であるババカール・セック前CFPT校長への旭日双光章 の伝達式が開催され、ソンコ首相 らセネガル政府要人、JICA田中理事長、同セネガル事務所代表等が参加しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01522.html
○日本企業連絡会の開催
10月11日、伊澤大使は、当地訪問中の田中JICA理事長の同席の下、日本企業連絡会を開催し、セネガルにおける各社の活動や今後の見通しについて意見交換しました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034kzv7ygeZc87th3bFFHkmiSxx6863Yejiawqn1uNeeHaKRen4YNgLyDEYXDQ6kJLl&id=100078921276471
○セネガル産業・通商省主催「産業・通商・中小企業・中小製造業戦略会議」への出席
17日、伊澤大使は、セネガル産業・通商省主催「産業・通商・中小企業・中小製造業戦略会議」において登壇し、セネガルの産業発展に向けて、戦略、人材育成およびセネガルの宣伝が重要である旨を強調しました。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0paRrsUHDg63HnStXDr6p7wWxCprbUeXPjw1MSVJjANMMbAXNn1ZYDgBAXM4FDD6Tl&id=100078921276471
○在外公館長表彰式:パパ・マガトゥ・ゲイ日セネガル友好協会(ASENI)会長への伝達式の実施
10月19日、パパ・マガトゥ・ゲイ日セネガル友好協会(ASENI)会長に対し、伊澤大使から、日セネガル関係強化への貢献を称え、在外公館長表彰が授与されました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01532.html
○伊澤大使によるジョップ国防大臣表敬
10月24日、伊澤大使は、ジョップ国防大臣を表敬し、我が国がカザマンス地方で実施する地雷除去活動支援について意見交換しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01543.html
○伊澤大使によるJICAチェアへの参加
10月29日、ダカール大学(UCAD)において、JICAセネガル事務所主催で日本の発展の教訓をテーマにするJICAチェアが開催されました。伊澤大使は京都大学の高橋基樹教授とともに参加しました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01545.html
○JETROアフリカビジネスデスク
ジェトロ(日本貿易振興機構)は、アフリカでの事業展開を目指す法人及びアフリカですでに事業を展開している法人を対象に相談サービスを提供しています。
対象国は20か国で、セネガルも対象国に含まれていますので、活用をご検討ください。
【詳細】
https://www.jetro.go.jp/services/africa_bizdesk.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3vePD6Ntz0xjeO_a3yCxw3b_An2F6r7apxSQiUKG-mzCYiKcNYm7xnQmc_aem_fgnxm1eyZLBAn6WZF5me2A
○当館が所掌する4か国(セネガル、カーボベルデ、ガンビア、ギニアビサウ)の政治経済関連の一般情報は、毎月上旬に当館のHP「セネガル基礎情報」及び「新着情報」に「在セネガル大使館月例報告」として掲載しております。ご関心のある方は以下のリンクをご参照ください。
(参考)月例報告:https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01078.html
6 広報・文化便り
○第37回俳句コンクール作品募集開始
在セネガル日本大使館はこの度、第37回俳句コンクールの作品募集を開始しました。概要は以下のリンクのとおりです。どなたでも応募いただけますので、みなさまの作品をお待ちしております。
応募期限:2024年12月20日
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01535.html
○セネガル柔道連盟主催「2024年柔道日本大使杯」の開催
10月26日、ダカール市内のマリウス・ンジャイ・スタジアム(Stade Marius Ndiaye)にて、セネガル柔道連盟の主催により「2024年柔道日本国大使杯」が開催されました。
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01541.html
○「2024年空手大使杯」の開催
11月30日、「2024年空手大使杯」が以下のとおり開催されます。どなたでも見学できるため、関心のある方はご覧ください。
日時:11月30日(土) 16時ごろから各階級の決勝戦が始まります。
会場:Stade Marius Ndiaye
○当館では、日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本関連行事のほか、知り合いの方のご活動等についての情報を( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )までお知らせください。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。当館HPやSNSへの掲載は随時行います。
○当館SNSでは、セネガルで開催されるイベントの告知や当館の活動報告を行っています。他にもたくさんのコンテンツがありますので、定期的にアクセスしてみてください。また、日・セネガル関係強化のため、ご関心のある投稿のRTやシェア等、皆さまのご協力をぜひお願いいたします。
TW:https://twitter.com/JapanEmbSenegal
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100078921276471
Instagram:https://www.instagram.com/japanembsenegal/
----------------------------------------------------------------------
[在セネガル日本大使館メールマガジン]
○本メールマガジンに関するご意見・ご要望は以下のメールアドレスあてに送信してください。新規配信登録のご希望もこちらまでお寄せください。
( mailmagazine-sn@dk.mofa.go.jp )
○参考ホームページ
首相官邸ホームページ ( www.kantei.go.jp )
外務省ホームページ ( www.mofa.go.jp/mofaj/ )
当館ホームページ ( https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )
○発行:在セネガル日本大使館
Ambassade du Japon au Senegal
Boulevard Martin Luther King, Dakar, Senegal (B.P. 3140)
TEL :(+221)33.849.55.00
FAX :(+221) 33.849.55.55